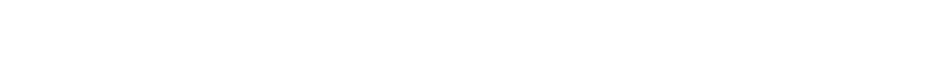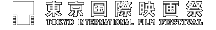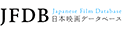東京国際映画祭公式インタビュー:
『i ai』
マヒトゥ・ザ・ピーポー(監督/脚本)

4人組バンドのメンバー、コウ(富田健太郎)。「色のない世界」で冴えない日々をおくっていた彼を音楽の世界に導いたのは、愛をいっぱいに抱えた破天荒な男ヒー兄(森山未來)だった。オルタナティブバンドGEZANのフロントマン、マヒトゥ・ザ・ピーポー(1989〜)が初監督した本作は、時代が差しだすお仕着せのファンタジーに踊らされず、自らの心に耳を傾け、一度限りの人生を噛み締めて生きようと誘う純度の高い傑作。青春映画、音楽映画などの要素を持ちながらも、生きること、愛することへの熱狂的なメッセージが明石の海にこだまする、感動的な作家映画ともなっている。
一般公開はまだ当分先のため、具体的なキャストやタイトルに関する取材は避けたが──映画祭上映をご覧になった方々は、きっとこの部分をいち早く語りたいに違いない──、音楽や小説の世界に通じる監督の映画観をここではご堪能いただきたい。
――本作をアジアの未来部門に選出した石坂健治シニア・プログラマーが、「ミュージシャンが余技で作ったのとは違う本格的な作品」と評しており、作品を見てなるほどと思いました。
マヒトゥ・ザ・ピーポー監督(以下、マヒト監督): ミュージシャンがつくる映画は、CMやミュージックビデオ的な瞬発力のある絵が2時間続くのが多いけど、俺はそうしたものは映画でやる必要がないと思っているから、そこはかなり意識しました。
――この作品はどこを切っても、監督の顔がよく見える。音楽や小説(2019年「銀河で一番静かな革命」を発表)に触れたことのない人間でも、監督の訴えたかったことが明確に感じとれる作品であり、新しいタイプの映画になっています。
マヒト監督:上映が終わって、映画館を出た後も人生は続いていくけど、いまの時代はその境界が曖昧で、すごく混乱していますよね。コロナが収束しないなか、戦争が起こり、ダメな脚本家が書いたストーリーみたいな現実があって、ファンタジーと現実が表裏一体になっていて。監督の自分が映画のどの部分にも表れているとしたら、そうした時代のありかたを敏感に受け止めて、揺るがしたい気持ちがあるからです。

――監督が本作の制作前に公表したステートメントには、以下の一節があります。「気配、匂い、重さ、そういった画像からこぼれ落ちる存在の影にこそ、人の呼吸がある。わたしはその時間を撃ちたいのだ。」「今、この世界に出回っている絵のどれだけが撃ち抜かれた瞬間なのだろうか?」これは既成の映画に対する挑戦状。マニフェストです。
マヒト監督:ただ笑って泣いて楽しめる作品ではなく、映画を見て生まれた感情が、見終わった後も、暮らしに息づいている作品にしたかった。映画は暗闇にいる2時間だけでなく、もっと長い時間軸で人に働きかけるものだと思うんです。だから、たとえ死を題材にしていても、希望を持てるようにしなければならず、ヒー兄のキャラクターにどう希望を見出すのか考え抜きました。
――ヒー兄のモデルになったのは一体どんな人物だったのですか。
マヒト監督:自分やバンド仲間を音楽の道に誘ってくれた、年上のバンドマンです。CDが何万枚売れたとかライブに何万人来たとか、そんな数字上の記録はないけど、世間が言う幸せや成功とは無縁なところで魅力的な生き方をした人で、彼の存在を通して、ありきたりな価値観に対する抵抗や自分が創作活動を続ける上で受けた影響を、映画に焼きつけました。
――オーディションで選んだ出演者とプロの俳優の混成キャストでしたが、一体感がありアンサンブルが見事でした。
マヒト監督:プロにしか出せない境地はもちろんあると思いますけど、演技経験のない人にしか出せないピュアさもあるはずで、キャストに関しては両者をハイブリットに混ぜ合わせようとしました。
――青春映画、音楽映画、ヤクザ映画など、さまざまな要素を持ちながらも自分色に染めており、監督の映画の趣味の広さを感じたのですが?
マヒト監督:好きな監督は沢山いますよ。『i ai』に直接何か影響を与えているかというと違うけど。映画のあちこちに顔が見えるという、さっきの話に乗っかるなら、俺は大林(宣彦)監督が好きですね。あのダダ漏れしている感じとか。映画祭で作品を見た人では、寺山修司を引き合いに出す声も聞きますけど。(エミール・)クストリッツァとかレオス・カラックスも好きで、自分が映画好きになったルーツには彼らの存在があります。
――この映画を特別なものにしているのが、ストーリーをはみ出してそこかしこに溢れる独白、キャラクターの内なる声に込められた言葉の力です。生きること、愛することに関するあれらの独白は、監督の体内から抑えがたく湧き出てきたもののように感じました。
マヒト監督:独白はもちろん映画のために書いたものですが、ずっと自分の内部にあって、血肉となっている言葉です。世界が混乱している以上、人も同じだけ混乱しないことには両者の間に共鳴はない。それゆえ、映画は完璧であってはならないと思い、一連の独白を入れたんです。
――写真家の佐内正史さんが撮影監督を務めて、明石の海や街を印象的に切り取っています。
マヒト監督:神戸生まれの(森山)未來さんが、「これは自分が子供の頃に見ていた海の話だ」と撮影前に言ってくれて、その言葉を意識しました。神戸から明石にいたる海岸線は、波も低くて静かなぶん、彼岸みたいな雰囲気があって、死を意識させるところがある。撮影に関してはその印象をまるごと切り取りたくて、ヌケがよくてカラッとしてるけど、一抹の寂しさがある感じを大事にしました。
――最後に聞きますが、監督にとって赤はどんな色でしょう。
マヒト監督:最初から映画で赤を強調しようと思っていた訳ではなくて、自然と赤くなってしまったというのが本音です。スタイリストの宮本まさ江さんが俳優の衣裳を数着持ってくると、無意識裡に赤系統ものを選んでいるんですから。でも考えてみたら人間は、黄色人種でも黒人でも白人でも、みな赤い血が流れている。だから、いちばん根源的な色だと自分が感じていることは事実です。それぞれを分断する記号が今日では氾濫しているけど、血の色はみな同じで、そういう根源的なイメージを映画に取り入れたかったということもありました。
第35回東京国際映画祭 アジアの未来部門
『i ai』

監督:マヒトゥ・ザ・ピーポー
キャスト:富田健太郎、森山未來