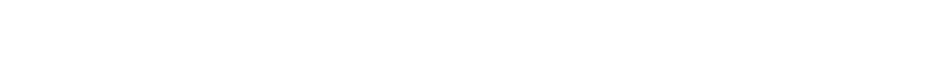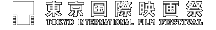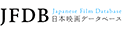東京国際映画祭公式インタビュー:
『1976』
マヌエラ・マルテッリ(監督/脚本)

チリのピノチェト独裁軍事政権が国を制圧して3年目の1976年。海辺の別荘を改修するために訪れた裕福な医師の妻カルメンは、その地の司祭から傷を負った青年をかくまってほしいと頼まれる。引き受けたことで平穏だった彼女の日々は、大きく変わることになる――。女優としてチリで活動し、監督に転じたマヌエラ・マルテッリの長編デビュー作は、1976年のチリの男性優位社会を、ブルジョワ女性の視点で描いたドラマ。細やかな演出が光る。
――最初にタイトル『1976』の所以についてお聞きします。
マヌエラ・マルテッリ(以下、マルテッリ監督):最初は自伝的な視点でこの物語を書こうと思いました。1976年は私の祖母が亡くなった年なのです。彼女は落ち込んで鬱状態で亡くなりました。私の家族は個人の問題だと片づけていました。祖母はアーティスト志望でしたが、余裕がなくて希望を果たせずに亡くなったのです。
そして1976年は、独裁政権下のなかでも過酷な年でもありました。このタイトルを付けることで、祖母が亡くなった命日を、新しく生まれ変わる誕生日にしたいという思いを込めました。
――この時代を描くにあたってリサーチも綿密にされましたか。
マルテッリ監督:リサーチには長い時間をかけました。主に「口伝的なもの」、言葉で伝えられるものを重視しました。というのも、女性について書かれたものはあまりなかったからです。歴史についての本は、ほとんど男性が男性の視点で書いていて、女性についての話が少ないのです。
主婦や母親たちと話をして、彼女たちが実は政治的な役割を担っていたということを知りました。当時、実際に政治的に関わっていた人たちと話もしました。本やアーカイブ、チリの記念美術館でもリサーチしましたが、人の話を聞くことがもっとも役に立ちました。
――上流階級の女性がこの時代を体験するという形で、まとめた理由は何でしょうか。
マルテッリ監督:私がよく分かっている視点から描いた方がいいと思ったのです。私は貴族階級の生まれではありませんが、かなり恵まれた育ちだと思っています。良い学校に行けたし、修士課程の大学院まで行けました。チリの多くの人たちよりは恵まれている環境ですね。
この視点から題材を捉えたいと思いました。犠牲者の視点から独裁政権について語られることが多いと思いますが、その視点では私が話す権利がないように思いました。立場的にブルジョワ女性は居心地が良くない。逆に難しいから語ることで共感を得られる気がしたのです。
――その発想で脚本をまとめるにあたり、どういう結末をつければいいと考えたのですか。
マルテッリ監督:結末を最初に決めていました。1950年代か60年代に祖父が撮った8ミリ映像を見つけたのです。デジタル化して見たのですが、カラフルな映像で、私の宝物になりました。美しい誕生日やお祝い、結婚式や休暇の日々が映っていました。その映像の中で、祖母は鬱っぽく、何かが欠けている印象でしたが、ある瞬間に強いイメージが映されました。祖母が娘のひとりにケーキをあげようとしていて、すごく微笑んでいるけれども、完全に心は何かに囚われているような表情、幸せとメランコリーが同居した、強い印象的な目をしていました。これを最後の場面にしようと思いました。
彼女は、最終的にはブルジョワ生活に戻っているけれども、何が起こっているかは理解している。祖母は“新しい女性”としてそこにいる。チリの人たちの多くは、見ないふりをし、沈黙し、“静かなる共謀者”になっていると思います。

――アメリカに留学されていますが、国外に住むことによって視点は変わりましたか。
マルテッリ監督:変化はありましたが、海外で滞在する時間のほうが長くなったので、うまく表現できません。ただチリはとてもアメリカの影響を受けています。アメリカがクーデターにも関わっていたし、独裁政権下の新しい経済システムというのも、アメリカがすごく影響しているのです。
チリの若い経済人たちを、ネオリベラリズム発祥の地であるシカゴで勉強させるなど、アメリカの影響は半端ではありません。私は今、ドイツに住んでいますが、アメリカがラテンアメリカを植民地にしていると強く感じます。
――今、ドイツにお住まいということで、この作品は共同製作がアルゼンチンとカタールですが、これにはなにか理由があるのでしょうか。
マルテッリ監督:プロデューサーがインカというアルゼンチンの製作会社を紹介してくれたので、申し込みました。チリの資金だけでは足りなかったので、共同制作にせざるを得なかったわけですが、インカは予算の半分以上を出してくれました。撮影後にドーハの映画団体が資金を出してくれて、ポストプロダクションができました。
――監督になられた経緯は? 現在はヨーロッパにお住まいですか。
マルテッリ監督:以前はイタリアで映画に出演したりしていました。イタリアの演劇の学校を終えてチリに戻り、フルブライト奨学金に受かってアメリカに3年居ました。その後またチリに戻って、8年ほどこの映画を作るために奔走しましたが、いざ撮影しようとしたらパンデミックが起こってしまい撮影できませんでした。
私のパートナーが音楽家の研修プログラムに受かって、ドイツに滞在するということになり一緒に行きました。この作品の完成後もドイツに住んでいます。
――演技も学ばれたのですね。なぜカメラを撮る側にまわられたのですか。
マルテッリ監督:初めから監督になりたいと思っていました。10代のころから演技をしていましたが、それは映画撮影の現場に入る良いチャンスだと思ったからです。そのうち同じような役ばかり来るようになって、もっと技術を身につけないといけないと思いました。
ただ女優は、映画の世界に入る足掛かりとしては面白いし、その経験が監督をするにあたって役立っています。
――監督として目指している人はいらっしゃいますか。
マルテッリ監督:50年代から70年代初頭のいわゆるクラシカルな映画の監督が好きです。アントニオーニ、タルコフスキー、ヒッチコック、トリュフォー、ゴダール、ロッセリーニも好きです。50年代、60年代いろんな人がたくさんいるので、この人と断定するのは難しいですが、チリの監督ではラウル・ルイスとアルド・フランシアが好きです。
第35回東京国際映画祭 コンペティション部門
『1976』

監督:マヌエラ・マルテッリ
キャスト: アリン・クーペンヘイム、ニコラス・セプルベダ、ウーゴ・メディナ