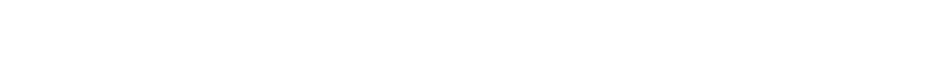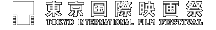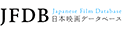東京国際映画祭公式インタビュー:
『This Is What I Remember(英題)』
アクタン・アリム・クバト(監督/脚本)

ロシアに出稼ぎに行って、記憶喪失になった男が20年ぶりに故郷のキルギスに戻ってきた。息子は男をさまざまな場所を連れ歩き、村の人々に会わせるが、記憶は戻らない。周囲の人たちに複雑な感情をもたらしながら、男は故郷に留まった――。『明りを灯す人』(10)などで日本でも知られるキルギスの名匠、アクタン・アリム・クバトの最新作は、キルギスの現在をストーリーに込める。監督の故郷、思い出の場所も映像に描きこまれていて監督自身も主演している。
――この作品はどういうアイデアから始まったのでしょうか。
アクタン・アリム・クバト(以下、クバト監督):行方不明だった人が23年経って見つかって、故郷に戻ったといニュースをインターネットで読んだことが始まりです。
――記憶喪失に陥った人が、現在のキルギスに戻ることによって、さまざまな事象が浮かび上がってくる。そのような発想で進められたのですか。
クバト監督:私にとって大切なのは、記憶を失った男にまつわるストーリーです。主人公がどう振る舞うかではなくて、周りがどう反応するかに注目しました。変化は主人公ではなくて周りに起こるわけです。記憶を取り戻すのは本人ではなく、息子や男の妻、友人たちなのです。これは記憶を無くした人が生まれ変わる映画です。
――新鮮だったのは、キルギスの今が作品に反映されていることでした。
クバト監督:はい。現実を歪めていないはずです。家族関係、家族の中の女性の立場、宗教、そして環境問題ですね。キルギスは現在、ゴミの溢れる社会になってしまっています。ソ連崩壊後、キルギス人はゴミを全く気にしなくなってしまった。環境汚染の問題もあります。
私は環境も清潔にするべきだと考えます。映画を作る時はいつも、創作とドキュメンタリーの間を取るようにしています。
――ご自身が主演された理由はなんですか。
クバト監督:私が主役を演じるのはこれが3本目になりますが、俳優になるつもりはありませんでした。私の外見は俳優向きではないと思っていますから。(笑)最初に演じたのが、『明りを灯す人』(10)という作品でした。一風変わった優しいイメージの俳優を探しましたが、見つからなかったので自分が演じることにしました。以後は自分自身を想定して脚本を書いています。
――息子の役も実際の息子さんなのですね。俳優と伺いました。
クバト監督:私は三部作をふたつ撮っていますが、最初の三部作の2本で息子が主演を務めています。少年時代と若者時代を演じているわけです。最初の三部作は私のこれまでの人生、自伝として描いたものです。私の息子が私の少年時代を演じていたのは単に私に似ているからです。
今度は過去の自分についてではなく、自分の周りに起こっていることを撮ろうと思いました。実際に生きて、感じてきたことを題材にして作品を撮っています。この映画は2回目の三部作、最後の作品になりますが、これまでの作品の全てを込めようと思いました。私が生まれ育った村、村を吹く風、架かる橋、住人たちとか、そうした要素を反映させました。

――同時に現在キルギスで起こっている状況を、記憶喪失の男を通じて浮かび上がらせていったわけですね。
クバト監督:主人公が記憶を無くしたことは無駄ではなかったと伝えたかったのです。今のキルギスの人たちは家族の関係ですとか、宗教に対する考え方とか、環境について気にしなくなってしまっています。私はこの映画を通じて、忘れないで欲しいと訴えたかったのです。人は常に理性を持って物事に向き合わなければいけません。
――何故、三部作なのですか。
クバト監督:三部作はよく使われている手法ですね。私の場合、最初の三部作では、1本目が子ども時代、2本目が少年時代、そして3本目が若者時代というふうに設定しました。そして2回目の三部作では、現在の私の状況を描いているわけです。
――映画監督を志した理由をお聞きしたいです。
クバト監督:私は映画監督になろうと思ってなったわけではありません。画家、絵を描くのが仕事で、たまたま映画スタジオに職を見つけました。10年ほど美術を担当して、映画製作に参加しているうちに、別の撮り方があると思いました。
たたまたま偶然にドキュメンタリーを監督してみないかという話をもらいました。それが“The Dog Was Running”(原題“Bezhala sobaka”)という作品です。幸い好評で新作の話が来るようになりました。
――映画の最初の場面で林を印象的に捉えていて、ラストは主人公が木を塗るところで終わりますね。
クバト監督:樹木は命の象徴です。木を最初と最後に出すことで、人の人生の始まりと終わりの象徴も込めています。この主人公はなぜかこの林に惹きつけられます。作品の中で、聖職者が、「かつてあった愛が林で失われた」と口にします。この言葉と主人公の行動は、記憶が戻る希望を抱かせる象徴になっているわけです。
また、白は透明感、正常さを象徴するものです。そして、主人公は樹木を白い色で塗ることで自分のこれまでの人生を真新にする意味合いも込めているわけです。春になると木を白く塗るという習慣がキルギスにはあるのですが、主人公が白く塗ることで、失われた愛が戻ってくるという意味合いも込めました。昔は、キルギスの住居は土で固められていて、壁を白く塗っていました。
――キルギスの映画状況を教えてください。
クバト監督:ソビエト連邦の崩壊前、予算はソ連の中央政府から出ていました。崩壊後は細々と映画の撮影を続けていましたが、デジタル技術が出てきて新しい段階に入りました。現在では年に70本くらい映画が撮られています。ただ、すべてが質の高い映画というわけではありません。
――主人公の設定がロシアで記憶喪失になったというのは、ある意味キルギスを象徴する意味合いもあるのですか。
クバト監督:ソビエトが崩壊した時には、キルギスは農業国で産業がありませんでした。大勢の人が海外に出稼ぎに出ることになりました。出稼ぎ先で一番多いのがロシアでした。キルギスの人口は700万人ですが、100万人が出稼ぎに出ていると言います。
――次の作品はどちらの方向になるのでしょうか。
クバト監督:別の題材を撮りたいと思っても、どうしても自分に戻ってしまいます。自分は何者なのかと考えてしまうのです。ただ三部作は撮らないでしょう。ちょっと時間が足りないと思います。
第35回東京国際映画祭 コンペティション部門
『This Is What I Remember(英題)』

監督:アクタン・アリム・クバト
キャスト:アクタン・アリム・クバト、ミルラン・アブディカリコフ、タアライカン・アバゾバ