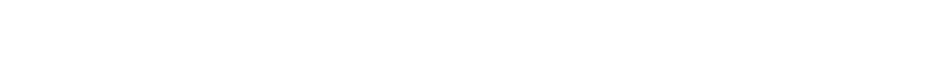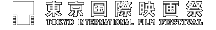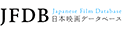東京国際映画祭公式インタビュー:
『孔雀の嘆き』
サンジーワ・プシュパクマーラ(監督/プロデューサー/脚本)

19歳のアミラは、両親の死後4人の弟妹を連れて首都コロンボに移住。しかし難病を患う長女の心臓手術のために大金が必要となり、高額の給料を保障してくれる会社で働きはじめるが、そこは子どもを外国人に斡旋する闇の組織だった――。『フライング・フィッシュ』(11)でデビューした、サンジーワ・プシュパクマーラ監督の長編4作目。自伝的要素を軸に、スリランカの抱えるさまざまな社会問題を浮き彫りにする人間ドラマ。一服の絵画を思わせる映像美を誇るスリランカの俊英監督に、映画への思いを語ってもらった。
――妹さんの死が本作制作のきっかけと伺いました。大切な人を失った悲しみを乗り超えて映画を作ろうとしたのはいつ頃ですか?
サンジーワ・プシュパクマーラ監督(以下、プシュパクマーラ監督):1996年に妹を亡くしました。私が大学の受験勉強をしている最中でした。その後、首都コロンボの大学でジャーナリズムを学んでいたのですが、スリランカの映画をたくさん見るようになり、“私にも語りたい物語がある”と感じました。
そこで思い切って映画監督になるために、ジャーナリズムから方向を変えました。そして初めて撮ったのが『フライング・フィッシュ』、(11)、その後『バーニング・バード』(16)。2014年からこの作品に取りかかり、完成まで7年かかりました。
――脚本は、どのように書き進めましたか?
プシュパクマーラ監督:今のスリランカが直面している不安定な社会政治や経済破綻、中国による干渉という背景の中で、妹の物語を描きたいと思いました。ずっと以前からこういう状況になるのではないかと危惧していましたから。もちろん、これまで歳を重ねて表現のテクニックも少しはマシになってきたので、中国をアンダートーンで背景に置き、メインのお話はわかりやすく。シンボリックなものや比喩的なものも織り込んで、観てくださる方が察してくださるようにしました。
例えば、養子斡旋会社の黒幕は中国人ですが、一度も登場しません。あえて前面に出さないほうが、より強く伝わると思ったからです。そして東京国際映画祭での上映ではその目論観が当たった手応えが得られて、とても嬉しかったです。
――養子斡旋会社を仕切る中年女性マラニは、“善と悪”の混在したキャラクターだとおっしゃっていましたが?
プシュパクマーラ監督:人間には、誰でも“陰と陽”があります。私にも裏がありますし、私が最も敬愛している人にも裏はあるのです。それを以前の作品より、今作でさらに強く描きたいという気持ちに駆られました。ドストエフスキーのように、もっともっと人間の内面に分け入っていきたい。それがフィルムメーカーにとって大切なことだと実感しているところです。人間は、そもそも複雑な動物。その複雑さの要因として、善と悪の混在があるのだと思います。
――監督がおっしゃったことをキャストたちが少ないセリフで体現しています。とくにアミラ役は監督自身を投影していると思われますが、キャスティングの決め手は?
プシュパクマーラ監督:心の中にあまりに多くを抱えていると人間というものは、その想いを言葉にすることができません。言葉よりもジェスチャーや行動でしか自分たちを表現する術がないのです。アミラの役は他の俳優が決まってリハーサルもやったのですが、いろいろな理由で降板させました。おっしゃる通り、アミラは私を投影した役ですから、私が一番彼を把握しています。その私の理解の50%でも理解してくれる俳優がいたらいいなと思って探したのですが、なかなか見つからなかった。そんな時に、ナディー役のディナラ・プンチヘワさんが友人だと言って紹介してくれた青年が、アカラン・ブラバシュワーラだったのです。彼は数分間ほかの作品に出たことがあり、コマーシャルにも1本出ていたようですが、私は見ていません。そこでリハーサルをして、彼に決めました。

――多くの監督が「子ども、素人、赤ちゃんを撮るのは難しい」とおっしゃいますが?
プシュパクマーラ監督:その通りです。これまでの『バーニング・バード』『フライング・フィッシュ』そして『孔雀の嘆き』を三部作と考えていますが、その作品すべてにアマチュア、プロフェッショナルでない人、赤ちゃんと仕事をしています。ナディー役のディナラさんでさえ2作目ですからね。ほんと子どもを演出するのは大変! ひとりが泣き止めば、ひとりが泣き出す。多くの時間を犠牲にしなければならないし、忍耐力もかなり必要です。しかも今回は、コロナで動きが制限されている上にマスクもして暑いし、雨で撮影が中断されるし…。とにかく、二度と子どもの演出はやりたくないですねぇ。(笑)
――とはいえ、子どもや赤ちゃんのクローズアップは印象深い余韻を残していますし、雨の風景も効果的。ワンカット、ワンカットが絵になっていて、監督がおっしゃっている「映画は芸術だ」の意味がわかりました。
プシュパクマーラ監督:絵画を見るのが好きです。今日も美術館でシスレーの絵画を見てきました。シスレーの絵画にとても影響されています。レンブラントやカラヴァッジョなどの色彩や画面の構図にも影響を受けています。この映画を撮る時に、彼らの絵をもう一度見直してシーンを練り直したりもしました。
この映画を絵画的だとおっしゃってくださいましたが、考えてみるとこの物語はとても悲劇です。そしてとても重たい物語。ですから映像だけでも、とても美しく撮りたいと思ったのです。
――監督ご自身のバックグラウンドは、決して恵まれた環境ではなかったように思います。それにも関わらず大学に行き、留学し、映画を学び、映画監督として注目を集めていらっしゃる。今、ご自分を振り返って?
プシュパクマーラ監督:学び続けることがモットーです。毎晩寝る前に、必ず新しいものを発見したり、学ぼうとしています。私は、まだ何も成し遂げていません。いままでの歩みは、微々たるものです。44歳にもなって、何もやっていない。時々、愕然とします。今は階段を登り続けているところですが、将来、絶対に成し遂げてみせます。
――恵まれない環境から抜け出せた要因は?
プシュパクマーラ監督:情熱と勇気です。映画に対するパッションがあったから。映画のためなら何でもするという気持ちがあります。
妻にも「まず映画が先だよ」と伝えてあって、彼女も理解してくれていますから。私は、自分のやりたいことはやり通すタイプの人間です。だからといって、まったく妥協しないわけではありません。ただし、私が妥協した場合、次のステップで必ず事は成し遂げられると思った上での妥協です。そういう意味では、私は常に戦う人、ファイターであると思っています。
第35回東京国際映画祭 コンペティション部門
『孔雀の嘆き』

監督:サンジーワ・プシュパクマーラ
キャスト:アカランカ・プラバシュワーラ、サビータ・ペレラ、ディナラ・プンチヘワ