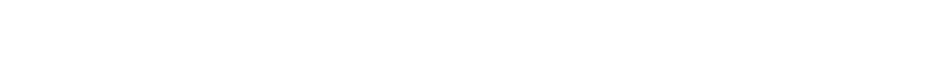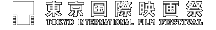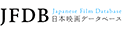東京国際映画祭公式インタビュー:
『第三次世界大戦』
マーサ・ヘジャーズィ(俳優)

地震で妻と子どもを失い、建築現場の日雇いで働くシャキーブ。その工事現場でホロコーストの映画を撮影することになり、彼は強制収容所のエキストラに。ところがヒトラー役の俳優が急病で倒れ、彼がその大役に大抜擢されたことで、彼の生活は一変し…。物騒なタイトルだが、驚きの設定を使いながら、今現在世界中の人々が少なからず感じている抑圧と不安によって起こる悲劇を描いた力作だ。物語の転換点で重要なパートを担う、シャキーブの知人で聾唖の女性ラーダン役を演じたマーサ・ヘジャーズィに、現場での話などを聞いた。
――この映画に出演された経緯は?
マーサ・ヘジャーズィ(以下、ヘジャーズィ):監督によるオーディションがありました。監督はイラン映画に多く出ている、知名度の高い役者さんを好まなくて、顔が知られていない新人を探していました。私は短編映画には出ていたのですが、長編は初。それで、友達にこのオーディションのことを教えてもらって受けることにしました。
監督は覚えていなかったのですが、実は10年前に出演した短編映画で、ホウマン・セイエディ監督が審査員を努めた映画賞をいただいたことがあって、初対面じゃなかったんです。監督にオーディションでお会いした時に「10年前にあなたから賞を貰ったことがありますよ」と言ったら思い出してくれました。(笑)
――オーディションでは本作の脚本を使ってましたか?
ヘジャーズィ:脚本全部を渡されたのは、役が決まってからですね。オーディションは何度もありましたが、その一部を使っていました。ホウマン・セイエディ監督が作っている作品はみんな大好きだし、超有名な若手監督なので、彼の映画に出るチャンスがあるなら、どんな作品かわからなくても、脚本を読まなくても受け入れちゃいますね。
――監督は俳優としても活躍されてますが、監督としての人気と俳優としての人気には差があります?
ヘジャーズィ:彼は役者としてもテレビに出ていてすごく人気ですし、人気テレビドラマの監督も努めています。どちらも大人気のスーパースターといえるでしょう。
――自分の役が決まって、脚本を全部読んだときはどう感じましたか?
ヘジャーズィ:自分の役、ラーダンのたどる運命を読みながら、「生きてほしい、生きてほしい、生きてほしい」と思いながらページをめくっていました。最終的には彼女は死んでしまいますが、脚本を熟考すると、そうなるべきだったと思えたんです。なぜなら、結果的にシャキーブがヒトラーみたいになってしまうから。だからこれは脚本にあるべきだと納得したのですが、やはり可哀想で仕方がなかったです。
――ラーダンは手話の話者ですが、手話についてのトレーニングは?
ヘジャーズィ:私自身はやったことがありませんでしたし、身近に聾唖の方はいなかったので、手話は全くの初体験です。そのため、トレーナーをつけて練習しました。家でも鏡の前でずっとやったり、耳の不自由な方と会って手話で喋ったり、台本の台詞だけでなく、自分の言葉を手話で表現することを、3~4か月近く続けてました。また今年、アカデミー賞作品賞を受賞した『コーダ あいのうた』を参考に観ました。もちろん手話のタイプが違うので、手話のモーションに関しては役に立たないのですが、手話の話者の仕草や表情、表現の仕方を見るために何度も見たことは役に立ちましたね。
――『コーダ あいのうた』や『ドライブ・マイ・カー』など、手話の話者が登場します。映画のトレンドのひとつのように感じますね。
ヘジャーズィ:作品に手話を取り入れたことについては、スタッフも含めみんな監督に「トレンド読んだよね」と口々に言ってましたよ。実はイランでも昨年、手話を使っている映画が2本あったんです。世界的に流行ってると思いますね。最近感じるのは、手話が画的にすごく美しいものだがから、映画にはうってつけということ。
本作のラーダンは、腕に何重ものブレスレットをつけていますが、それは監督が意図的に指示しました。というのも、彼女が怒っている時は、ジャラジャラジャラとやっているから。手話を語るときに音による表現もプラスできたんですよ。

――監督は誰もが知るスーパースターですが、実際はどんな方?
ヘジャーズィ:会ってみると、普通の人です。みんなと一緒にご飯を食べたりして、会った瞬間も友達だと思ったくらいです。彼は学校で演劇を教えていて、普段から若い人たちと朝から晩まで接しているので、コミュニケーションを取りやすいキャラクターなのでしょう。一緒に日本に来てほしかったのですが、残念ながら今回は来られませんでした。会えばよくわかると思いますよ。
――役者さんが監督をやるというと、役者の気持ちもわかってくれますよね。気配りを感じた瞬間は?
ヘジャーズィ:彼はいつも私たちの気持ちを凄くわかっていました。例えば、撮影現場では、カメラが回る10分前に必ず監督と話す時間があるんです。なんで今ここにいるのか、今どういう気持ちでこの人と会わないといけないのか、とか。
そこで自分のキャラクターをよく知ることはできたし、彼が役者としてやってほしかったことがその都度よく理解できるんです。こういうやり方をしてくれたのは、役作りにはとても助かりますし、それは監督自身が俳優だからできることなんでしょう。
――監督からの特別な指示はありました?
ヘジャーズィ:「アンネ・フランクのことを思い出して」と監督に言われました。「あなたは彼女みたいに、匿われているこの場所を自分の家だと思わなければいけない」と。それは非常に役立ちました。
――かなりチャレンジで、つらい役どころでしたが、終わってからも役が残りませんでしたか?
ヘジャーズィ:自分の撮影パートが終わってひとりでテヘランに戻ったんですが、ものすごく孤独を感じて、まるで自分が捨てられてしまったような気持ちになってしまいました。すべての撮影が終わってみんなと会った時に、やっとその気持ちから解放されましたね。それまで泣いて寝て、泣いて起きる。鬱になりそうだったんですよ。映画の中で散々ひどい目にあったのに。
――ホロコーストの映画をイランで撮影している、というびっくり設定についてはどう感じましたか?
ヘジャーズィ:チャレンジですね。先日、この作品を劇場で見た時、ヒトラーが出て来るシーンでオーディエンスが笑ったのを見て、私も笑っちゃったんですよね。第二次世界大戦のころ、イランには北側のポーランドからたくさん難民が入ってきていますし、戦争の歴史自体はみんなよく知っていますし、ホロコーストを描いた他国の作品も知っています。でも、イラン映画で、ホロコーストをテーマにした映画はありません。だから、これからどういうリアクションがくるか楽しみなんですよね。
第35回東京国際映画祭 コンペティション部門
『第三次世界大戦』

監督:ホウマン・セイエディ
キャスト:モーセン・タナバンデ、マーサ・ヘジャーズィ、ネダ・ジェブレイリ