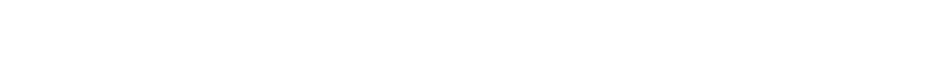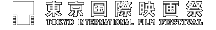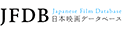東京国際映画祭公式インタビュー:
『アシュカル』
ユセフ・チェビ(監督)

革命によって建設が中断、廃墟と化したジャルダン・ド・カルタージュ地区で黒焦げの死体が発見された。自然発火としか考えられない状況のなか、ファトマとバタルのふたりの刑事が捜査に当たるが、同様の事件が連続し、謎はさらに深まっていく――。チュニジアの新鋭ユセフ・チェビの初長編監督作は、ジャンル映画の衣を巧みに纏った問題作。旧政権が残した巨大な廃墟の威容が映像インパクトを高め、政治的テーマを浮かび上がらせている。
――作品を興味深く拝見しました。作品が生まれた経緯を教えてください。
ユセフ・チェビ(以下チェビ監督):場所がきっかけになりました。母がジャルダン・ド・カルタージュに家を建てることになり、このエリアを私もよく知ることになりました。実はこの場所は古い遺跡のある所で、徒歩で1kmのところにこのジャルダン・ド・カルタージュがあります。とても印象的でした。古い遺跡のすぐ近くに、現代の廃墟があるのです。
――ジャルダン・ド・カルタージュはかつてのベン=アリー政権が設計したものですね。
チェビ監督:旧政権としては、この都市をチュニジアの最も近代的で富裕なイメージ、権力の象徴としてここを創ろうとしていたのです。2011年に革命が起こり、この都市の工事がそのまま止まりました。私がこの場所を知ったのは2016年ですが、辺りをいろいろ歩いてみて、とても奇妙な感じがしました。空き家や廃墟に私が見られている気持ちでした。私は何か作品ができる可能性を感じました。
――インスピレーションが降ってきたのですね。
チェビ監督:政治的な要素も入れつつ、それ以上に奇妙さを際立たせる。私の好きな形の作品にしたいと思いました。ジャンルとしてはフィルム・ノアールで、捜査をしていく展開です。まるで迷路みたいな場所で、ふたりの登場人物が何かを探している。でも、彼らは現実の中でそれを探しているので、決して見つけられない。なぜなら、彼らが追っているものは、超自然なものだからです。
――それにしても、発火する身体という発想自体がとてもユニークだと思いました。
チェビ監督:私としては、焼身自殺をモチーフにしたのです。廃墟が直線的でミニマルな工作物があり、対照的なものを探していました。形が自由に変化する、抽象的なものを考えていた時に、炎や発火というアイデアを思いつきました。チュニジアの革命が始まったのは、ある焼身自殺がきっかけでした。そしてその結果として、このエリア一帯の建設が止まったわけですから。火を連想させることで、この廃墟と化した建物の中に、まるで命を宿したような感覚が生まれると思いました。
――イメージされたのは焼身自殺なのですか。
チェビ監督:焼身自殺は政治的な行動ではありますが、同時に、神秘的なもの、宗教的な行為でもあると思います。かつてペルシャでは、預言者モハメッドの顔を聖なる火で描いています。私たちはモハメッドの顔そのものを絵にすることはできないので、描く時には顔が聖なる火で覆い隠すのです。自分の体に火をつけるというのは予言的な行為でもあるということです。
――これが長編第一作だと思いますが、このアイデアが生まれて実現するまでにかなり時間はかかりましたか?
チェビ監督:脚本を書き始めてから初上映まで3年かかっています。予算は少額でしたが、プロデューサーとともに十分なだけの資金を集め、すぐに制作に入りました。
最後のシーンは、ショッキングと捉える方が多いのも理解はできます。チュニジアでは来年2月に公開する予定です。
――ジャンルとしていわゆる刑事物のスタイルで始まって、最終的にはSFを想起させるような展開になります。監督はジャンル映画が好きなのだと思ったのですが?
チェビ監督:そうですね。今回は現実的なものからスタートしたいと思っていました。というのも、チュニジアでは焼身自殺はそんなに珍しいものではないのです。チュニジアの現実に近いところから出発し、徐々に超自然もしくはファンタジー的なところに持っていきたいと思っていました。
ロケ地がSFっぽいのも幸いしました。現実からちょっと距離を置いて間接的に見せるのが好きです。というのも、映画はそもそも、目に見えないもの、理解できないものを伝えるものだと思っています。

――焼身自殺がそれほど珍しくないということで、ラストシーンに寓意性を持たせてくると思います。
チェビ監督:私としては選択肢を提示したいと思っていました。最後の場面は集団自殺であると言えるかもしれないし、人々が別の世界に昇っていく、もしくは渡っていく、あるいは真実を目にするということかもしれません。宗教や信仰に対する疑問も投げかけています。信仰によって何をするのかにも疑問を投げています。最後のシーンで大事なのは、ファトマという人物が何かを目撃しているという点です。彼女が目撃しているものは奇跡、もしくは断末魔、あるいは悲劇かもしれませんが、彼女が目撃して終わるという点を大切にしています。誰もが自由に解釈できるようなものにしたいと思いました。
――チュニジアで映画監督を志すということにご苦労がありますか。この作品もフランスとの合作ですよね。
チェビ監督:チュニジアでの映画製作は大変です。ほとんどフランスとの合作です。チュニジアでも映画の製作費は出ますが、ほかからの資金は必要です。最近はアラブからの参加も増えてきています。私は8、9歳くらいの時から映像の虜になり、以来、監督を目指しました。
日本の尊敬する監督は黒沢清、塚本晋也。フランスだと、ロベール・ブレッソンですね。画はラジカルでありながら、とても繊細で小さなディテールとか小さな現象に凄く心を奪われるというところが、良いと思っています。ブレッソンと黒沢の間くらいを目指したいですね。
――最後に、ドキュメンタリーも撮られていますが、今後もドキュメンタリーとフィクションを並行して監督しようと考えていますか?
チェビ監督:はい。ドキュメンタリーは今も手がけています。新作はチュニジアのアンダーグラウンドのミュージシャン、若い人たちを取り上げています。
第35回東京国際映画祭 コンペティション部門
『アシュカル』

監督:ユセフ・チェビ
キャスト:ファトマ・ウサイフィ、モハメド・フシン・グライヤ、ラミ・ハッラービ