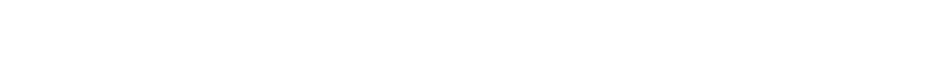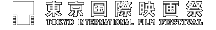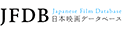東京国際映画祭公式インタビュー:
『突然に』
メリサ・オネルイ(監督)、フェリデ・チチェキオウル(脚本)

嗅覚を突然失った中年女性レイハンは、30年ぶりにドイツからイスタンブールに帰る。絶望した彼女は街を彷徨い、自分の居場所、新しい人生を求めていく。写真家で、演劇やビデオインスタレーション制作でも才能を見せるメリサ・オルネイが、脚本家のフェリデ・チチェキオウルの協力のもと、女性主導のチームで生み出した作品。人生の分岐点に差し掛かった女性の姿を、細やかな映像と情感で描き出す。イスタンブールの街が魅力的に映る。
――まず、この作品の成立までの経緯をお聞かせください。
メリサ・オネルイ監督(以下、オネルイ監督):最初のアイデアは「見えない女性」、他人の目に映らない女性を描いてみたいという思いがありました。このアイデアについて脚本のチチェキオウルさんと話すようになり、2年半ぐらい脚本を練り込みました。ただ言葉を紡ぐのではなく、視覚的なイメージが浮かぶように心がけました。できたものを撮影のマリアム・ヤヴズに見せ、さらに視覚を際立たせました。
フェリデ・チチェキオウル(以下、チチェキオウル):監督は言葉だけではなく、フィーリングや感触を作品に織り込みます。時には監督は自分の人生から材料を引き出しますし、想像で付け加えることもあります。
――主人公の置かれている状況も興味深いですね。
チチェキオウル:彼女が彷徨うイスタンブールという街は、海に囲まれている街なのですね。ボスポラス海峡で混じりあった地中海の暖かい水と黒海の冷たい水が、まるで母の子宮であるかのように街を包み込んでいる。それがイスタンブールなのです。主人公は「見えない人間」になろうとします。彼女は自分が属する場所を探すのです。しかし家や故郷というものはどこにも見つからない。彼女はドイツのハンブルクからイスタンブールに戻ってきました。ハンブルクもイスタンブールと同じく港湾都市ですが、ずっと寒くて、飛んでいるかもめさえ種類が違います。イスタンブールと比べると匂いも少ない。匂いを失った主人公はイスタンブールの混沌とした状況を恋しがる――こういう風に話を作っていきました。

――主人公の30年ぶりの帰郷にも意味を持たせたかったのでしょうか。
オネルイ監督:家に帰るという形ではありません。主人公は人生から逃げて、逃げた先に留まるのです。その行動が彼女を変えていきます。主人公は、「これが自分の故郷なのか」と常に問いますが、彼女の家族がいる場所はもはや彼女の家ではありません。それが分かって、彼女は自分の居場所を探さないとならないわけです。これは家を求めて探し回る話です。
――居場所を探す女性というのは監督自身の想いが反映されているんですか?
オネルイ監督:私たちに重なるところが多い作品です。私にとっては、主人公を信じることができるかどうかというのが鍵でした。それができれば、この映画は成功するだろうと思っていました。観ている人が、映画の最後に、それまでずっと止めていた息をようやく吐くことができるという、そんな感じが表現できれば良いなと。それは成功したと思います。
――この作品はどのぐらいの日数で撮影されて、最も苦労されたことはなんでしょう。
オネルイ監督:24日間です。50か所もロケをしたので、時間がないのが一番の悩みでした。一日12時間くらい撮影していました。事前に2週間ほど準備の期間を取って、撮影のマリアム、監督助手、プロデューサー助手たちと、さまざまな場所でリハーサルをしました。おかげで時間を節約することができました。
――もともと監督は写真家ですね。映画に表現の場所を変えた理由を教えてください。
オネルイ監督:写真家として働いていた時も、ある瞬間を切り取ることに興味がありました。最初の短編も、瞬間の集まりを作品にしました。瞬間を切り取ることから、ストーリーを語ることに変更した理由は、フェリデ・チチェキオウルの存在です。私自身はいろいろな瞬間についてのアイデアがあります。彼女と一緒に仕事をすることでストーリーに仕上がるわけですね。
――おふたりはどこで出会ったんですか?
チチェキオウル:出会いはオネルイの最初の短編ですね。瞬間を切り取ったものを見て、すごいなと思いました。それが最初です。
オネルイ監督:私が大学の修士過程にいた時に、彼女は映画とテレビ制作の学部長でした。私自身、イスタンブールを出たことは進学のために短期間ありますが、主人公のように長年離れたことはありません。
――トルコの映画事情はどんな感じでしょうか。
オネルイ監督:トルコのインディペンデントの映画産業というのは、資金に限りがあります。そういうわけで共同制作をせざるを得ない場合が多いですね。この映画は文化省にもサポートをもらっています。ドイツとセルビアとトルコの3か国の共同制作となりました。デジタル化が進んだことで、映画界は少し活気が出てきています。
――監督が一番影響を受けられたという存在はどなたでしょうか?
オネルイ監督:マヤ・デレン、アンドレイ・タルコフスキー、アニエス・ヴァルダ、クレール・ドゥニ、ルクレシア・マルテル、そして私の先生(チチェキオウル)ですね。

――女性主導で映画を作るのは、トルコの映画界では珍しいことですね。
オネルイ監督:確かに女性ばかりのチームですね。プロデューサーは産休で来られなかったし、アート・ディレクター、それから照明、助監督も全部女性です。こういうことはトルコでは珍しいことです。
――次の作品のご予定はありますか?
オネルイ監督:もうすでに先生と一緒に書き始めています。次回の作品はダンスについてのものなのですが、今回のこの『突然に』が「個人の自由」あるいは「個人の成長」というテーマだったとしたら、次の映画というのは「反抗」、それから「繋がり」がテーマになります。
第35回東京国際映画祭 アジアの未来部門
『突然に』

監督:メリサ・オネル
キャスト:デフネ・カヤラル、オネル・エルカン、シェリフ・エロル