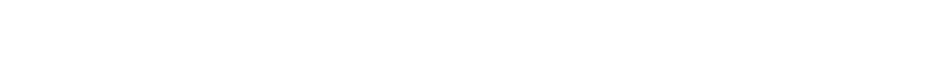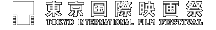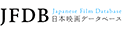東京国際映画祭公式インタビュー:
『ライフ』
エミール・バイガジン(監督)

カザフスタンの大都市から辺境まで。仕事の大失敗をきっかけにすべてを失った男、アルマンが繰り広げるあてどなき旅を、圧倒的に美しい映像で綴った170分の大作『ライフ』。人生甘くない、だが甘く愛おしく感じられるのは、そういった崖っぷちのときだ、という思いから描かれた物語は、ひとつの出逢いによって生まれた。そのいきさつを、エミール・バイガジン監督本人に聞いてみた。
――18年の『ザ・リバー』以来の来日ですね。東京の滞在はいかがですか?
エミール・バイガジン監督(以下、バイガジン監督):とても満足しています。東京は、私にインスピレーションを与えてくれる都市です。2018年は宿泊先から銀座に通っていたんですよ。今回は、宿泊も映画祭も銀座ということで、とても嬉しく思っています。日比谷公園にいると、とても落ち着くのでよく散歩してますよ。
――まず、このような大作を選んだ理由を教えて下さい。
バイガジン監督:この映画を撮らなければ、という考えが起きたんです。私は自分の直感を信じていますので。また、経済的にもこの映画を撮れる可能性がありました。4作品目が大きな映画祭で賞をいただいた(『ザ・リバー』/ヴェネチア映画祭オリゾンティ部門監督賞)ということもあって、経済的にもこの超大作に耐えうる状況があったのはラッキーでした。
――『ライフ』は誰にでも起きうる崖っぷち状態と現実逃避が描かれ、身につまされる映画でした。着想源は?
バイガジン監督:10年前、ある方に出会ったことがきっかけです。その方はたくさんの借金を抱えていて、とても苦労していました。彼と話したことがずっと記憶に残っていたんですが、10年経ったことで彼をモチーフにした映画にしようと思ったんです。彼が抱えていた問題は私が抱えていた問題よりもよっぽど深刻でしたが、彼は私よりも人生そのものを愛していたように感じます。あいにく彼とは一度会ったそれきり。そのときもすごく短い時間のおしゃべりだったんですけどね。その時に話した印象や話した時の感覚を思い出して描いたんです。彼はまさに人生と戦う人でした。
――彼から聞いた実体験はどの程度脚本に入ってるんでしょう?
バイガジン監督:ほとんどはフィクションです。彼の印象や強く心に残った感情や感覚をもとに、私が考えました。
――監督ご自身が追い詰められて崖っぷちに立たされた経験は?
バイガジン監督:誰にでもありますよね。もちろん私も。何かとても大変なことが起こった時に、そこから逃げ出したくなるのは、誰しも考えることです。ただ、そこから我に返って、何とか問題を解決しようとするものだと思います。生と死の狭間の状況で、人が心の中で認めることは、生きることへの愛なのではないかと思います。

――それをこれほどの大作にするための期間は?
バイガジン監督:映画全体に費やした年月は、3年半です。準備には5か月かかりました。私にとっての5作目を、大作にしたかったんです。ちなみに『ライフ』というタイトルは、これ以外にしっくりくるタイトルが思い浮かびませんでした。10年前にその男性に会った時からそのタイトルは頭の中にあったんですが、何とかしてこのタイトルを変えようとしたんですよ。でも、できませんでした。運命ですね。
――3年半もの撮影となると、役者もスタッフもよく完走しましたね。
バイガジン監督:じつは私たちはもっと早くに終わると思ってたんですよ。(笑)でも、コロナによる隔離期間やら検疫期間ができてしまったので…。3年間、アルマン役の俳優は同じ服を着ているので、きっと飽きたんじゃないかな。(笑)映画の中で起こっている出来事は、ひと月ほどの出来事なのに、それを3年かけて撮っているので、おそらく俳優さんは飽きてしまったのではないかと思います。
――同じ季節に撮影しなければならない苦労もありますね。
バイガジン監督:そうなんです。色々な苦労がありました。大作ということもありますし、3年がかりとなると俳優たちやスタッフも他の仕事が決まっていましたから、そちらにも行かなければいけないとか。同じ時期に合わせなければいけないということなどを含め、色々なことがありました。
季節を逃してはいけないということと同時に、エネルギーを逃してはいけないということもあります。監督ですら、ひとつの映画を作っているとエネルギーを消費し、ひとつの作品をちゃんと終わらせてからまた次の所へ行くというふうにしなければエネルギーが涸れてしまいますからね。でも、それができませんでした。
――パンデミックのせいですね。
バイガジン監督:でも、パンデミックによって活発に活動ができなかったことを実は内心喜んでいました。(笑)スタッフ達、チームの皆に、なぜ今、休憩をとらなければいけないのかということを説明することができたし、その間に私自身も休みが取れたからです。私自身が休憩を取り、力を溜める必要があったんですよ。当然ですが、検疫によるマイナスの側面もありました。この場所は撮影できるが、この場所はできないなど、パンデミック前では起きないトラブルによって力が損なわれていくんです。私のスタッフは10人以上いますが、小さいスペースで皆マスクをしていなければいけないということもとても大きなストレスでした。カザフスタンで、マスクをつけて歩くということは初めての経験でしたからね。
――マスク生活に慣れることも大変ですよね。
バイガジン監督:それだけでなく、現実的な問題として、マスクをしている人の映り込みもあったんですよ。大都市で行った撮影時、当時皆マスクをつけて歩いていました。すると、歩いている人が撮影現場に近づいて来たりすると、映像の中にマスクをつけている人が映りこんでしまいますから。そんな苦労は初めてのことでした。
第35回東京国際映画祭 コンペティション部門
『ライフ』

監督:エミール・バイガジン
キャスト:イェルケブラン・タシノフ、カリナ・クラムシナ、イェルジャン・ブルクトバイ