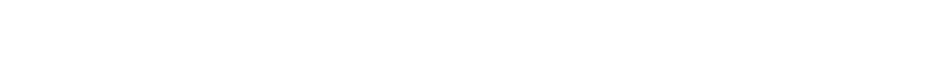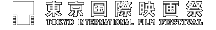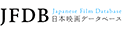東京国際映画祭公式インタビュー:
『カイマック』
ミルチョ・マンチェフスキ(監督/脚本/エグゼクティブ・プロデューサー)

©2022 TIFF
北マケドニア、首都のスコピエ。ミルチョ・マンチェフスキ監督の生まれ故郷を舞台にした、大人のラブストーリー『カイマック』。2組の夫婦それぞれにひとりのキャラクターが介在することによって描かれる、リアルでセクシュアルな物語だ。それらは、単に三角関係や嫉妬などありきたりな恋愛模様ではなく、実際に起きそうな事件の連続。ブラックなユーモアがたっぷり詰め込まれた本作について監督が語ってくれた。
――タイトルにもなっているカイマックは、公式の資料ではお菓子とされていますが、劇中で出てくる同じ名前のものは違いますよね。
ミルチョ・マンチェフスキ監督(以下:マンチェフスキ監督):お菓子じゃなくて、クリームなんです。乳製品で、バターとフェタチーズの間のような物で、甘くないんですよ。パンに塗ったりして使う、バター代わりの乳製品ですね。牛乳を煮込んで上澄みになったクリームの部分を掬って作ったもので、イギリスのクロテッドクリームにちょっと似てますね。
――タイトルにした理由は何ですか?
マンチェフスキ監督:上澄みを使ったクリームなので、「美味しいところを取る」という意味があるんです。マケドニアで「カイマックを取る」というのは、その意味で使われています。我々誰もが人生で良いところを取りたいじゃないですか。なかには成功する者もいれば、失敗する者もいます。それがまさにこの映画の中のキャラクターに起きるわけです。
――プロットの着想は、このタイトルからですか?
マンチェフスキ監督:いえ、この題名は後からつけました。キャラクターのひとりが、市場でカイマックを売っていますよね? それで、タイトルとしていいメタファーになると後から思って、後から名付けました。
そもそも、この物語のアイデアは、大人向けのラブストーリーを作りたいと思ったところから始まっています。最近の恋愛映画はかなり幼稚なものが多いですからね。なので、もう少し大人向けの話題、浮気や不倫、3Pなどなど、アダルトな部分をフィーチャーしたかったんです。ちなみに、知能が遅れている子どもを代理母として利用するというアイデアは、実際に起きた事件をベースにしました。
――本作の中でも最悪なエピソードが、本当だったとは…。
マンチェフスキ監督:それが人生の悲しい、そして面白いところだと思います。つまり、一番あり得ない、あってはならない事実は実際に起きている、ということです。私が12年前に作った『ビフォア・ザ・レイン』も、あまりにも現実離れした物語でしたが、現実だったんですよ。ドキュメンタリーとして撮らなければ誰も信じてくれないような物語でしたね。
――過激なシーンもありますが、役者の方々がこの脚本を読んだときはどういう反応をされてましたか?
マンチェフスキ監督:とても気に入ってもらえました。俳優陣は、とても豊かでリッチなキャラクターを演じる機会を楽しみにして、自分達の大きなチャンスだと思ってくれたようです。なぜならば、この映画に出てくるあらゆるキャラクターは、大変複雑だからです。俳優たちにとっては、意欲が湧く仕事だったはずです。

――大爆笑の3Pのシーンで、振り付けや演出はどう決めたのですか?
マンチェフスキ監督:僕の方が気兼ねしてしまいましたね。(笑)ある程度の振り付けはしましたが、僕はどちらかと言うと、彼らの自発的な演技に頼りました。即興の部分もありますし、あえてクローズアップで映して、全体がわからないようにもしました。願わくば僕はそのシーンで、ロマンティックでありながら大変現実的であるということを目指しました。
――リハーサルなどの準備期間はどれくらいでした?
マンチェフスキ監督:僕は常に、キャスティングとリハーサルに長い期間を費やします。例えば、キャスティング。今作は3~4か月かかりました。その後、選んだ人たちと3週間のリハーサル期間を設けました。リハーサル中に僕が一番集中したことは、彼らの行動の原点や理由ですね。なぜ彼らはこういう行動を取るのか、ということを突き詰めていきました。
そのゴールは、彼らの行動から真実を聞き取ることです。そうすることで、リハーサルで俳優たちが到達したいろいろな真実をちゃんと覚え、僕も彼らが到達した真実をちゃんと覚えていて、両者がちゃんと撮影の時にそれを再現できるんです。
――今のお住まいはニューヨークですよね。ニューヨークで暮らすことによって、マケドニアに対して新たに見えてきたということはありますか?
マンチェフスキ監督:違った文化圏に住むと、より周りのものに気がつくものです。それと、より努力をし、一生懸命働こうという気持ちが湧いてきますね。特に常に何かが起きている街ニューヨークという所では。(笑)
マケドニアは時間が止まっているような気がしますよ。マケドニアで育った時からずっと、自分はアウトサイダーだという気持ちがありました。ニューヨークに移り住んで、その気持ちが確信に変わりましたね。映画監督という自分のキャリアの中でも感じています。なぜなら、僕の映画の教育はアメリカですが、テイストはどうしてもヨーロッパ。そのせいか、僕は今の立場を探求し、いろいろ考える機会が多くなってきました。
――本作をマケドニアの人たちはどうご覧になると思いますか?
マンチェフスキ監督:僕の作品には2種類のオーディエンスがいると思っています。それは、マケドニアの人たち、それとそれ以外の人たちです。マケドニアの観客たちは「あなたは、我々を世界にどういうふうに見せているの?」ということを気にするんですよ。まるで、マケドニアのコマーシャルを作ってほしいと思ってるのではないかと思うくらい、他者からの見え方というものを気にしています。僕は決してマケドニア人のことを描いているのではなく、人間を描いているわけですから、それは困るんですよね。例えばスコットランド人が『マクベス』を見て、「なんで僕達を殺人者として描くの?」とシェイクスピアに文句を言うようなものです。その一方で、諸外国の観客にはヘンな期待があるものなんです。マケドニアがどういった場所なのか、ということに興味を持って惹かれているんですね。それで、彼らが持つ、その国に対する先入観や差別が正しくあってほしいという期待があるんです。これについては、エドワード・サイードの「オリエンタリズム」という本で書いているんですが、はっきり言ってしまうと、これは人種差別なんですよね。
――悲しいことですよね。それこそ勝手な先入観ですから。
マンチェフスキ監督:僕が描くものは人間主体なんですよ。イデオロギーではありません。イデオロギーの前にヒューマニズムと考え、信じています。それと同時にあらゆる映画が政治的でもある、と僕は思います。ただ、極端に政治的な作品はプロパガンダになってしまう危険性もありますよね。不幸なことに、その罠にかかってしまう映画関係者や、映画監督、または映画祭も存在します。そうすると、シネマの中から芸術性が吸い取られてしまうんですよ。
――そこを正すための使命感を持って作品作りをされているんですか?
マンチェフスキ監督:そうですね。でも、僕としてはそれが自然な映画作りです。こういう映画が、自然に僕の中から湧き出してきますから。
インタビュー/構成:よしひろまさみち(日本映画ペンクラブ)
第35回東京国際映画祭 コンペティション部門
『カイマック』

© Banana Film, Meta Film, N279 Entertainment, Jaako dobra produkcija, all rights reserved, 2022
監督:ミルチョ・マンチェフスキ
キャスト:サラ・クリモスカ、カムカ・トチノヴスキー、アレクサンデル・ミキッチ
東京国際映画祭公式インタビュー:
『カイマック』
ミルチョ・マンチェフスキ(監督/脚本/エグゼクティブ・プロデューサー)

©2022 TIFF
北マケドニア、首都のスコピエ。ミルチョ・マンチェフスキ監督の生まれ故郷を舞台にした、大人のラブストーリー『カイマック』。2組の夫婦それぞれにひとりのキャラクターが介在することによって描かれる、リアルでセクシュアルな物語だ。それらは、単に三角関係や嫉妬などありきたりな恋愛模様ではなく、実際に起きそうな事件の連続。ブラックなユーモアがたっぷり詰め込まれた本作について監督が語ってくれた。
――タイトルにもなっているカイマックは、公式の資料ではお菓子とされていますが、劇中で出てくる同じ名前のものは違いますよね。
ミルチョ・マンチェフスキ監督(以下:マンチェフスキ監督):お菓子じゃなくて、クリームなんです。乳製品で、バターとフェタチーズの間のような物で、甘くないんですよ。パンに塗ったりして使う、バター代わりの乳製品ですね。牛乳を煮込んで上澄みになったクリームの部分を掬って作ったもので、イギリスのクロテッドクリームにちょっと似てますね。
――タイトルにした理由は何ですか?
マンチェフスキ監督:上澄みを使ったクリームなので、「美味しいところを取る」という意味があるんです。マケドニアで「カイマックを取る」というのは、その意味で使われています。我々誰もが人生で良いところを取りたいじゃないですか。なかには成功する者もいれば、失敗する者もいます。それがまさにこの映画の中のキャラクターに起きるわけです。
――プロットの着想は、このタイトルからですか?
マンチェフスキ監督:いえ、この題名は後からつけました。キャラクターのひとりが、市場でカイマックを売っていますよね? それで、タイトルとしていいメタファーになると後から思って、後から名付けました。
そもそも、この物語のアイデアは、大人向けのラブストーリーを作りたいと思ったところから始まっています。最近の恋愛映画はかなり幼稚なものが多いですからね。なので、もう少し大人向けの話題、浮気や不倫、3Pなどなど、アダルトな部分をフィーチャーしたかったんです。ちなみに、知能が遅れている子どもを代理母として利用するというアイデアは、実際に起きた事件をベースにしました。
――本作の中でも最悪なエピソードが、本当だったとは…。
マンチェフスキ監督:それが人生の悲しい、そして面白いところだと思います。つまり、一番あり得ない、あってはならない事実は実際に起きている、ということです。私が12年前に作った『ビフォア・ザ・レイン』も、あまりにも現実離れした物語でしたが、現実だったんですよ。ドキュメンタリーとして撮らなければ誰も信じてくれないような物語でしたね。
――過激なシーンもありますが、役者の方々がこの脚本を読んだときはどういう反応をされてましたか?
マンチェフスキ監督:とても気に入ってもらえました。俳優陣は、とても豊かでリッチなキャラクターを演じる機会を楽しみにして、自分達の大きなチャンスだと思ってくれたようです。なぜならば、この映画に出てくるあらゆるキャラクターは、大変複雑だからです。俳優たちにとっては、意欲が湧く仕事だったはずです。

――大爆笑の3Pのシーンで、振り付けや演出はどう決めたのですか?
マンチェフスキ監督:僕の方が気兼ねしてしまいましたね。(笑)ある程度の振り付けはしましたが、僕はどちらかと言うと、彼らの自発的な演技に頼りました。即興の部分もありますし、あえてクローズアップで映して、全体がわからないようにもしました。願わくば僕はそのシーンで、ロマンティックでありながら大変現実的であるということを目指しました。
――リハーサルなどの準備期間はどれくらいでした?
マンチェフスキ監督:僕は常に、キャスティングとリハーサルに長い期間を費やします。例えば、キャスティング。今作は3~4か月かかりました。その後、選んだ人たちと3週間のリハーサル期間を設けました。リハーサル中に僕が一番集中したことは、彼らの行動の原点や理由ですね。なぜ彼らはこういう行動を取るのか、ということを突き詰めていきました。
そのゴールは、彼らの行動から真実を聞き取ることです。そうすることで、リハーサルで俳優たちが到達したいろいろな真実をちゃんと覚え、僕も彼らが到達した真実をちゃんと覚えていて、両者がちゃんと撮影の時にそれを再現できるんです。
――今のお住まいはニューヨークですよね。ニューヨークで暮らすことによって、マケドニアに対して新たに見えてきたということはありますか?
マンチェフスキ監督:違った文化圏に住むと、より周りのものに気がつくものです。それと、より努力をし、一生懸命働こうという気持ちが湧いてきますね。特に常に何かが起きている街ニューヨークという所では。(笑)
マケドニアは時間が止まっているような気がしますよ。マケドニアで育った時からずっと、自分はアウトサイダーだという気持ちがありました。ニューヨークに移り住んで、その気持ちが確信に変わりましたね。映画監督という自分のキャリアの中でも感じています。なぜなら、僕の映画の教育はアメリカですが、テイストはどうしてもヨーロッパ。そのせいか、僕は今の立場を探求し、いろいろ考える機会が多くなってきました。
――本作をマケドニアの人たちはどうご覧になると思いますか?
マンチェフスキ監督:僕の作品には2種類のオーディエンスがいると思っています。それは、マケドニアの人たち、それとそれ以外の人たちです。マケドニアの観客たちは「あなたは、我々を世界にどういうふうに見せているの?」ということを気にするんですよ。まるで、マケドニアのコマーシャルを作ってほしいと思ってるのではないかと思うくらい、他者からの見え方というものを気にしています。僕は決してマケドニア人のことを描いているのではなく、人間を描いているわけですから、それは困るんですよね。例えばスコットランド人が『マクベス』を見て、「なんで僕達を殺人者として描くの?」とシェイクスピアに文句を言うようなものです。その一方で、諸外国の観客にはヘンな期待があるものなんです。マケドニアがどういった場所なのか、ということに興味を持って惹かれているんですね。それで、彼らが持つ、その国に対する先入観や差別が正しくあってほしいという期待があるんです。これについては、エドワード・サイードの「オリエンタリズム」という本で書いているんですが、はっきり言ってしまうと、これは人種差別なんですよね。
――悲しいことですよね。それこそ勝手な先入観ですから。
マンチェフスキ監督:僕が描くものは人間主体なんですよ。イデオロギーではありません。イデオロギーの前にヒューマニズムと考え、信じています。それと同時にあらゆる映画が政治的でもある、と僕は思います。ただ、極端に政治的な作品はプロパガンダになってしまう危険性もありますよね。不幸なことに、その罠にかかってしまう映画関係者や、映画監督、または映画祭も存在します。そうすると、シネマの中から芸術性が吸い取られてしまうんですよ。
――そこを正すための使命感を持って作品作りをされているんですか?
マンチェフスキ監督:そうですね。でも、僕としてはそれが自然な映画作りです。こういう映画が、自然に僕の中から湧き出してきますから。
インタビュー/構成:よしひろまさみち(日本映画ペンクラブ)
第35回東京国際映画祭 コンペティション部門
『カイマック』

© Banana Film, Meta Film, N279 Entertainment, Jaako dobra produkcija, all rights reserved, 2022
監督:ミルチョ・マンチェフスキ
キャスト:サラ・クリモスカ、カムカ・トチノヴスキー、アレクサンデル・ミキッチ