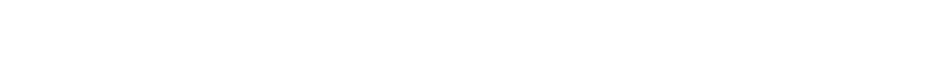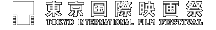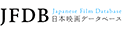10/31(月)Nippon Cinema Now部門『はだかのゆめ』上映後、甫木元 空(ほきもと そら)監督、青木 柚さん(俳優)、唯野未歩子さん(俳優)、前野健太さん(俳優)をお迎えし、Q&Aが行われました。
⇒作品詳細
司会・新谷里映(以下:新谷):まずは皆様から一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。
青木 柚(以下、青木):“ノロ”役の青木柚です。本日はお越しいただきありがとうございます。この作品はちょうど1年前の今くらいの時期に撮影をしていた作品で、こうして皆様の前で上映することができて大変嬉しく思っています。個人的にも非常に縁を感じている東京国際映画祭に、こうして作品とともに再び登壇することができ、大変嬉しいです。本日は短い時間ではありますが、よろしくお願いします。
唯野未歩子(以下、唯野):“母”役を演じた唯野未歩子です。本日はご来場いただきありがとうございました。先ほど舞台袖でエンディングの曲を聴きながら、様々なことを思い出して涙が出そうになりました。監督に色々と質問をされたい方もいると思うので、ぜひ今日は短い時間ですがよろしくお願いします。
前野健太(以下、前野):“おんちゃん”役を演じた前野健太です。今日はご来場ありがとうございます。四万十の風景と、今日の東京の夜のキラキラした風景が、今日の上映を通じて繋がったような感覚になっていました。本日はどうぞよろしくお願いします。
甫木元 空監督(以下、監督):監督を務めた甫木元 空です。今日はありがとうございます。先ほど柚くんも言っていましたが、1年前に撮影をした作品に皆さんから拍手をいただいて、やっと映画として完成したような実感ができました。今日は短い時間ですがよろしくお願いします。
新谷:まず私から監督に1つ質問をさせてください。監督は大学生の頃から青山真治監督に映画を教わり、この作品でもその影響があったと伺っておりますが、具体的にどのような影響や言葉があったのか、お聞かせいただけますでしょうか。
監督:私は埼玉県出身なのですが、甫木元という名字のルーツであり、かつ祖父が暮らしている高知県を舞台にしていつか映画が撮れたら、と本作の脚本執筆よりも前から思ってました。そうして5年前に実際に高知へ移住をしたのですが、その後の脚本執筆の前のリサーチの段階で、青山監督に宮本常一さんの著作である「忘れられた日本人」という本を紹介してもらいました。それは民俗学の本なんですが、それを読みながら、祖父が毎日話していた言葉だったり、母親が動物に話しかけるときに使っていた他愛もない言葉遣いだったり、そうした日常の風景を切り取り、メモするようになりました。そうしたインスピレーションを与えてくれる本の紹介というきっかけを青山監督にいただく形で、本格的に本作の企画が始まることになりました。
新谷:その際の体験が脚本の中のセリフや行間が反映されているということでしょうか。
監督:そうですね、まずは最初に私が簡単な小説のようなものを書いて、それをそのまま映像化するのではなく、映画でしか表現できないものは何だろう、というのを改めて考えながら、脚本を作り直す作業を行いました。今回の東京国際映画祭では青山監督の追悼プログラムもありますが、いつか映画祭で一緒に作品を上映できたら、と夢を語るようにお互いに話していて、本来想定していた形ではないながら、この映画祭でその夢は実現したんだと思っています。これからも青山監督の作品は世の中で鑑賞され続けると思うので、青山監督との縁を大事にしながら、今後この作品も上映され続ける作品になっていけばと思っています。
新谷:俳優の皆さんにもお話をお伺いしていきたいと思います。観客の皆さんも作品をご覧になって感じたと思いますが、セリフは少ないながら、行間に情感が豊かに詰め込まれた作品でした。私たちが作品を観てそのように感じるという背景には、脚本の段階で俳優の皆さんが演じる上での難しさもあったのではないかと思います。演じるにあたり、どのように俳優の皆さんがこの作品と向き合われたのか、一言ずつお伺いできればと思います。
青木:ご覧いただいた皆さんはお分かりになると思いますが、ほとんどセリフがなく、呼吸をしながら演技を表現する、というスタイルになりました。脚本を読んだ段階でもちろんそうしたアプローチになることはわかっていたので、いわゆる通常の作品で言うところの「台本」とは違って、甫木元さんの表現した景色や音、匂いみたいなものを、感覚的に文章にされているように見えていました。だから1回読んだだけでは演じる上で頭が追い付かないこともあったのですが、実際に高知の撮影現場に入ってからは、東京で脚本を読んでいるだけではわからなかったニュアンスが、“ノロ”の家に行くことで結びつくという現象がありました。それが土地や空気の力であって、それによって“ノロ”の人物像を作り上げてくれたのだろうと今は振り返りながら思っています。
唯野:私の演じた母親は、監督の思いなどが色濃く反映されている役でした。ただ、単純な再現ドラマみたいにはしたくないよね、と監督とも話をしていて、そうしたコミュニケーションを通じて少しずつ役を作っていきました。
監督:キャストの皆さんに共通しているのですが、実際に現地に来て、少しずつ撮影を経ていくごとに、表情が変わっていく印象がありました。
前野:最初に脚本を送っていただいて読んだときに、まるでセリフが歌詞のようだな、と思いました。私は歌が好きなのですが、歌だとすればこれはただの歌ではないと感じさせるものがありました。演じる際にはある意味、歌うように表現をすればいいのかな、と思いながら準備をしていたのですが、実際に高知に行ったら現地の景色にかなり翻弄されてしまい、なかなかイメージしていたように自然に歌いながら演じるというわけにはいかなくなってしまったんです。そのせいで私のシーンはほとんどカットされてしまったのかな、と思います。
監督:そんなことないです。
新谷:ありがとうございます。今の皆様からのお言葉を受けて監督から一言いただけますか?
監督:唯野さんに関しては、僕の母親が残した日記とかを実際に読んでもらったりとか、独自のアプローチをしてくれました。正直僕も毎日天候、自然が色々な悪さをしてくるので、思い通りにいかない部分もすごく多かったのですけれども、それぞれ自分がそこにどうやっていればいいかをすごく考えていてくださったので、とても楽しく撮影することができました。
Q:今回の映画制作にあたって、監督の体験、経験等はあるのかについて教えていただきたいです。
監督:5年前に移住することになって、90歳の祖父が一人で暮らしていることを心配した母親がそこに行くのですが、母親の方が先に余命宣告をされました。そういうこともあって僕も高知に行くことになりました。そういう宣告をされても母は家族にも気丈に振舞い、家事をし、洗濯物を干し、普通の生活を続けていくわけです。ですが、終わりが見えているなかで、本当に些細な事や、動物だったり、日の光だったり、昨日とは違う燕が来ているだとか、ここに花が咲くようになったと言って生け花に花を挿したりとか、そういう自分の終わりが見えることによって、人間の生きる時間というのは変わっていくのかなというのが一緒に生活していて実感がありました。そういう些細な事といいますか、全てを映画の中に入れているわけではないのですけれども、少しずつそこで得たものを映画の中に取り入れて、映画として何ができるのかということを考えました。全部が全部自分の実体験というわけではないです。人から聞いた話とか、いろんな人の話が各人物のなかに入っていると受け取ってもらえたらと思います。
Q:高知県は四国でお遍路さんという文化があるなかで、死と生が曖昧になっていくような空気感があるような場所なのではと思ったのですが、演者の方も監督さんもそういった曖昧なものを作品を通して表現されたのか、それともたまたまそういう作品になったのかをお聞きしたいです。
監督:仰っていただいたように、高知県は、死と隣り合わせというわけではないですが、四万十川という暴れ川と呼ばれている川があります。沈下する前提で橋が作られている“沈下橋”という橋もあって、自然の猛威を、抵抗するのではなく受け入れる姿勢というか、色んな流れの中にある県だなと思っています。ある種、あの世かこの世かわからない感じというのは、僕も最初に高知県に行って色々調べているなかで感じていた部分ではあります。なにか自分の気持ちの中で現実の母親が亡くなっていて自分が残っているというのとは逆転しているような、母親が残っていて息子がそれを見ているという、少し現実と逆の願望も映画の中には少し込めて脚本の中に入れたというのはあります。
青木:最初の本を読んだ段階で、誰が生きていて誰がそうでないのかというのはわからないですけど、僕は特に正解のようなものは最初から聞いていませんでした。高知県に着いたときに、曖昧さを大事にしたいという話をしていたかはわからないですけど、監督になにかを質問しても返ってくる答えもあれば、そうでない答えもあって、きっとそういう言葉にできないものがこの映画で伝えたいことなんだということをすごく思いました。個人的にはわからないものの良さじゃないですけど、手放しのわからないというよりは、意志の入ったわからないというか、難しいのですけれども、そういう0か100とかではなく揺らいでいるもののような感覚でしかないのですけれど、そういうものを大事にしたいなと思っていました。それは作品のテーマとしてもですし、演じた役の概念のようなものにも通じていて、曖昧さはすごく大事な要素だったのではと個人的には思っています。
唯野:皆さんのお話聞いていて思い出したんですけど、死を描こうというときに、生きている人が生きてないみたいで、死んでいる人が死んでないみたいなところから死を発見していくというか、死を追いかけていくというシナリオに気づいたら、はまっていました。肯定しているというか優しさを感じる不思議なシナリオだなと思いました。
前野:“おんちゃん”は死者と生者を結ぶ妖精のような役というのを、最初に監督から聞いていた気がします。そして、とにかく高知の自然がすごかったです。撮影が終わって山や森を見たときにそれらの自然に顔が見えたんです。この映画を通して地球は圧倒的にあっち側にあるなと感じました。生きているもの、残されたものの温かみ、生きていかなければいけない、というものを感じました。
Q:高知の印象や撮影の中で自然に翻弄されたり自然によって見出されたシーンなど高知に関するお話がありましたら教えていただきたいです。
青木:僕は初めて高知に行かせていただいたのですが、誰も拒まない町というか受け入れられているのか、歓迎されているのかわからないけれど、「いていいですよ」という雰囲気がある土地だなと思いました。それから時間がゆっくりでした。どの地方に行っても同じように感じるのかもしれないけれど、自分が普段仕事している意識と切り離せられる時間が多かったような感覚でした。
唯野:青木さんの仰る通りだなと思います。太陽が近くて暑いけれど、足元に落ちる影はその分濃くて、まるで命がそこにあるような感覚でした。厳しさと大らかさが一緒にある素晴らしいところだなと思います。
前野:空き時間に宿でテレビを見ていたんですけど、四万十川の様子を中継しているチャンネルがありますよね?
監督:よく気づかれましたね。
前野:あれがたまらなくて。きっと氾濫すると危ないからっていう目的だと思うんですけど。四万十川に設置されている複数のカメラが時折切り替わるんです、夜になると赤外線カメラになったりもして。それをずっと見ていて大自然に包まれた暮らしであることにグッときましたね。あとは水がいいせいか、喫茶店がすごく多かったです。僕は喫茶店が大好きなので滞在している間に何とか巡らなくてはいけないという使命感に駆られて5店舗くらい巡ったんですね。特に「どなあ」というお店のコーヒーが衝撃的な美味しさでした。あと、皆さんがかつ丼を食べに行ったお店に数日後に一人で行ったんです。そこの大将から優しくされて意気投合してしまって、「ルンルン」というスナックに連れて行ってくださいました。なんで大将さんと吞み屋に行ってるんだって感じですが非常にいい時間でした。
新谷:とても行ってみたくなるようなお話をありがとうございます。それでは最後に監督から皆様に一言メッセージをお願いします。
監督:とても小さな家族の話ではあるのですが、やっぱり映画はお客さんに観てもらって完成するのだなと今日改めて実感しました。これから劇場公開して映画の旅が続いていきますが、少しでも些細なことでもいいので話題にしていただければと思います。また何度でも劇場で出会っていただけたら嬉しいです。本日はありがとうございました。
新谷:ありがとうございました。甫木元監督はBialystocks (ビアリストックス)というバンドで音楽活動もされていて11月にはポニーキャニオンよりメジャーデビューアルバムが発売されます。そのアルバムに映画のエンドロールにかかる「はだかのゆめ」も収録されていますので是非皆さんそちらもよろしくお願いいたします。