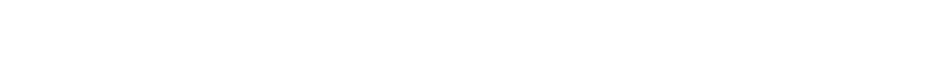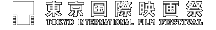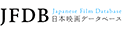東京国際映画祭公式インタビュー:
『ファビュラスな人たち』
ロベルタ・トッレ(監督/脚本/編集)

歳を重ねた5人のトランスジェンダーの女性たち。彼女らが集まり、30年前に亡くなった親友アントニアの願いを叶えようとしていた。彼女は埋葬されるときに、家族が望む男性のスーツを着せられていたが、お気に入りの緑のドレスのはずだ、と。そこで降霊術を行うことに…。ジェンダーへの差別ゆえに、最期の瞬間まで自分を奪われたトランスジェンダーへの思いを中心に、旧来の価値観に縛られた人々に対するメッセージを込めた『ファビュラスな人たち』。監督のロベルタ・トッレに、価値観の変容や旧来のジェンダー観の不当性を聞いた。
――物語の着想を得たきっかけは?
ロベルタ・トッレ監督(以下、トッレ監督):何年も前にポルポラ・マルカシャーノ(ポルポラ役で出演)の本を読んで、映画を撮ろうという風に思ったんですね。その本は70年代以降のトランスジェンダーの人たちについて色んな物語を描いており、映画化したいと思ったのがきっかけです。ただ、物語を自分のものに感じなければ、映画化は無理ですよね。
私は、その本でアントニアの物語と出会ったときに、自分の物語だと感じることができたんです。これはアントニアの物語として描いてはいますけれども、ほとんどのトランスジェンダーの人たちに起こることです。家族が彼女たちの肉体を奪ってしまい、女性なのに家族が勝手に望んでいる男の服を着せて埋葬してしまうとか。そんなことをしたら、彼女たちのそれ以前の人生まですっかり奪ってしまう。この物語に出会ったとき、自分ごとに感じることができたんです。
――監督も人生を否定されるような出来事があった?
トッレ監督:自分自身に起こったというわけではないんですけれども、非常に身近な人に起きました。すると、その人についての記憶まで家族が奪ってしまうんです。人が死ぬときにはその人たちの思いとともに、遺された自分たちの思いというのが非常に重要なわけですが、それらすべてを奪ってしまうというのは、非常に大きな暴力だという風に感じていました。
――トランスジェンダーの人権について大きく動きつつある今、本作が発表されたのはベストタイミングですね。
トッレ監督:じつは何年も前からこの映画について考えていて、ポルポラに初めて会ったのも2014年です。その時すぐに撮るつもりだったのですが、パンデミックがあったりで、なかなか実現できなかったです。不可抗力で遅れた分、世間的にはタイムリーな話になってしまいましたね。
――トランスジェンダーの物語として描いていますが、これは広く「女性」というジェンダーとしても解釈できますね。
トッレ監督:トランス、または女性、その両方の側における「暴力」はあると思いますし、それはかなりはっきりとした形で現れていると思います。特にトランスジェンダーの人たちにはそれがはっきりと現れるんです。映画の中で「私の体は政治的行為だ」というセリフがありますけれども、権力は弱いものに対して暴力を加えるもの。全ての人にとって、弱者は強いものから暴力を与えられる。これは常にあると思います。
――プロの役者ではなく、トランスジェンダー当事者をキャスティングしたのは?
トッレ監督:彼女たちの肉体も非常に大事なものです。それを使わないことは考えられなかった。フィクションのドラマとして書かれたものですが、彼女たちの言葉をプロの役者が代弁することはできなかったし、彼女たちの体と彼女たちが使う言葉が非常に大事だったということもあります。
――とすると、脚本上のセリフだけでなく、アドリブが多かったのでは?
トッレ監督:もちろん脚本はありました。でも、そのうえで即興でも演じてもらいました。彼女たちにとっては、自分自身の人生を語ることは、非常に簡単だったんですね。すごく慣れていたことなので、うまくいったと思います。
『死ぬほどターノ』(97)という作品が最初の長編作品なんですけれども、このメソッドでやりました。デビューから私がずっとやり続けていることなんですね。ドラマと即興の部分をミックスするというやり方は、時に素晴らしい結果をもたらしてくれますから。

――みなのびのびとしているのはそのおかげですね。
トッレ監督:多分そうだと思います。彼女たちはノンプロということで、用意されたセリフを役者のように演じるということはできません。それが非常に良かった。ただ、降霊術のシーンは、台本どおりに演じなければいけませんでした。時間を守って、順序立ててやっていかなければいけない部分なので、あそこはなかなか苦労したところで。笑ってしまったり、シリアスになれなかったりとか、何度もテイクを重ねたんですよ。
――イタリアのLGBTQ+のコミュニティとその認知は、どの程度進んでいるんでしょう?
トッレ監督:昔に比べれば随分良くなっているように見えるのですが、他国と比べてかなり遅れていると思います。表に見える部分はいいとして、それ以外のところではまだはっきりと差別的なものが残ってますから。
――すると、この作品によって訴えることがあるんですね。
トッレ監督:この映画が重要だったのは、彼女たちが自分たちの話を自分たちの姿ではっきりと表すこと。じつは、そういった映画は今まで撮られたことがないんです。トランスジェンダー本人が彼女らの人生を語る初めての映画なので、イタリアのLGBTQ+コミュニティにおいても非常に重要だったと思います。今までも彼女たちが出演した映画はありましたが、いつも脇役。今回は彼女たちが主人公ですから。それが非常に重要です。
本作はイタリアの大きな都市でいくつか上映会が行われ、彼女たちと一緒に回りました。すると、どこに行っても劇場はいっぱい。彼女たちはパフォーマンスするかのように、その場を楽しみ盛り上げてくれました。彼女たちの人間的な部分を、上映会をきっかけに広めることができたことも、大きな影響があるのではないかと思います。
――エンドロール前に、非常に効果的に彼女たちの若い頃からの写真を披露してますね。
トッレ監督:子供時代からの写真を全部見せてくれ、とお願いしました。なぜあのシーンを入れたかというと、彼女たちの旅を見せたかった、時間の移り変わりということを見せたかったからです。使う写真は私が選びましたが、大きなポイントは前と後。男の子だった時と、それ以降です。ふたつの人生を持ち、ふたつの違いがある。そういう感覚を彼女たちは持っているということを感じてもらいたかったんです。
――本作や彼女たちのおかげでイタリアの映像業界はちょっとずつ変わっていくと思います?
トッレ監督:ここ数年そういう傾向があると思います。特に、ハリウッドのように発信源として大きな業界が彼女らの人権について動いていることは、大きい影響を与えていますね。今年のヴェネチア映画祭でも、トランスジェンダーの主人公が登場する作品がふたつありましたから。
――映画業界、文化芸術の分野ではセクシュアルマイノリティへの差別や偏見を無くそうと必死に動いているのに、政治が動かないという世の中に対するジレンマは感じませんか?
トッレ監督:良い芸術というのは予見するものだと思っています。いつの世も政治は遅れていますよね。芸術の方が先を行っているから。
――イタリアでクィアフィルムが上映される機会は多いんでしょうか。
トッレ監督:LGBTQ+の映画祭はいくつかあります。ボローニャではポルポラ自身がディレクターを努めている映画祭があり、フィレンツェでは「Florence Queer Festival」もあります。でも、このジャンルはイタリアではメインストリームではないですね。どうにかしないと…。
――日本でも商業ベースに載せるものはストレート社会の男性が主導権を握っています。
トッレ監督:イタリアの映画界でも、男女間の差はすごくあります。イタリアの女性監督が撮った映画は全体の10~15%。まだまだ男社会ですね。それは、女性に対する信頼や評価が低いためです。そのため、一番重要な立場は男性が選ばれることが多いんですよ。ただ、撮影現場や編集などの裏方で働いている人たちは、女性が非常に多くなってきました。そこも変わらないとですね。
――イタリア初のトランスジェンダーの物語を作り上げましたが、次回作の構想は?
トッレ監督:本作に出ていたひとりに、母親役を演じてもらう作品を考えています。また、ポルポラ・マルカシャーノさんの本を、別の作品にしようとも考えていますが、その場合はプロのトランスジェンダーの役者を使おうかなと思っています。それによって、彼女たちの才能が評価されていくことを願って。
第35回東京国際映画祭 コンペティション部門
『ファビュラスな人たち』

監督:ロベルタ・トッレ
キャスト: ポルポラ・マルカシャーノ、ニコール・デ・レオ、ソフィア・メヒエル