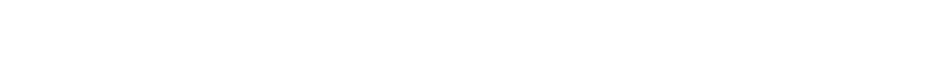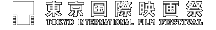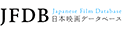10/25(火) ワールド・フォーカス部門『ラ・ハウリア』『ルーム・メイド』上映後、ジャン=エティエンヌ・ブラ(エグゼクティブ・プロデューサー)、ルー・シコト(エグゼクティブ・プロデューサー)、アルベルト・カルロ・ルゴ(ラテンビート映画祭プログラミング・ディレクター)をお迎えし、Q&Aが行われました。
⇒作品詳細
司会・笠井信輔(以下:笠井): 『ラ・ハウリア』は、アンドレス・ラミレス・プリード監督の初長編作品でございまして、カンヌ国際映画祭批評家賞グランプリを受賞し、プリード監督自身もカメラドール、新人監督賞にノミネートを果たしています。コロンビアで期待の新鋭です。この作品はラテンビート映画祭との共催作品となっておりますので、本日お越しいただいたラテンビート映画祭のプログラミング・ディレクター、アルベルト・カレロ・ルゴさんにまずはご挨拶をお願いします。
アルベルト・カルロ・ルゴ(以下、アルベルト):皆さま、お越しいただいてありがとうございます。今年、ラテンビート映画祭は19周年を迎えまして、東京国際映画祭との共同上映というのは今回が5回目になります。今回、『ラ・ハウリア』と短編の『ルーム・メイド』を一緒に上映した理由なのですが、プリード監督は、『ルーム・メイド』のルクレシア・マルテル監督に大いに影響を受けていまして、一緒に上映して観ていただくことに意義があると感じたからです。今回、『ラ・ハウリア』はラテンビート映画祭の作品として初めて今日この東京国際映画祭で上映させていただくのですが、ポルトガル語の映画をラテンビート映画祭から東京国際映画祭で2本上映することになっていまして、『パシフィクション』という作品も東京国際映画祭で上映いたします。
ルー・シコト:今回『ラ・ハウリア』を東京国際映画祭で上映できることをとても光栄に思います。これはプリード監督の初監督作品なので、特にこのような場で皆さまに観ていただけるのを嬉しく思います。あと私自身なんですけれども、8年前に東京芸術大学で学んでいたので、こうしてまた戻って来られることをすごく嬉しく思います。
ジャン=エティエンヌ・ブラ:日本は映画界において、歴史的にも大きな位置を占めている場所でもあるので、こういう場で私たちの作品を上映できるのがすごく嬉しいです。東京国際映画祭のプログラミングの皆さま、アルベルトさん、ここに呼んでくださってありがとうございます。
笠井:まずはラテンビート映画祭のアルベルトさん、最初にご質問がありましたらよろしくお願いいたします。
アルベルト:監督のアンドレス・ラミレス・プリードとどのようにして出会ったのか、どうしてこの作品を作るようになったのかを教えてください。
ルー・シコト:まず2016年にプリード監督とベルリン映画祭で出会いました。彼が短編の“El Edén”を出品していたときで、その“El Edén”に感動して、監督に私からコンタクトをして付き合いが始まりました。そこにジャン=エティエンヌも加わり、3人での関係が始まりました。まず、ジャン=エティエンヌと私がアソシエート・プロデューサーとしてフランスで一緒に組みたい、という風にプリード監督に提案しまして、プリード監督の初の長編映画を一緒に作ろうと持ちかけました。私たちはかなり感性が似ていまして、同じような背景を持っているので、それを融合させて、今回初長編という結果になりました。コロンビアとフランスと距離が離れていたのですけれども、毎週連絡を取り合って作品を進化させていったので、このような結果が生まれました。
笠井:このような若者の更生施設が、コロンビアには実在しているのでしょうか?
ジャン=エティエンヌ・ブラ:答えはイエスとノーです。監督は今回が初長編なのですが、今回焦点を当てたかったのはコロンビアの田舎で暮らす若者たちでした。施設に関しては非行少年を集めた更生施設というのはありますが、このまま、映画で観た通りではありません。少年少女が罪を犯したら収容される、このような壁のない、どこにでも逃げていけるような施設というのはコロンビアには存在しないので架空といえます。
Q:この映画は一部ドキュメンタリーのようなシーンがあったりとこれは本当にあった事件や監督の経験などをモチーフにした実体験に基づく映画なのか教えていただけますか。
ルー・シコト:監督はコロンビアの小さな町で暴力が親から子供に代々伝わっていくということについて調べていました。彼の過去の短編小説も今回の長編もそうなのですが、なぜ少年たちが父親に対してこれほどまでに憤りを抱いているのかということに監督自身が疑問を抱いて追求していました。今回の主人公に関しては償いを求めて自ら行動していくのですが、このような疑問点を出発点に監督は脚本を書き始めました。次にキャスティングの話になるのですが、出演している少年たちはみんなプロではなく、アマチュアの役者たちです。だからこそ役を演じるにおいて何かしら役と共通点がなければ演じにくいということで、暴力や麻薬に関して話すときに自然に見せられるようになにかしらバックグラウンドのある少年たちをキャスティングしたという経緯があります。だから所々でドキュメンタリーのように感じたのだと思います。ただ、ストーリー自体はすべてフィクションです。ドキュメンタリーに見えるのは監督の演出であってストーリーは作ったものです。
Q:2つの作品の監督が同じかと思っていました。青色の系統のユニフォームや黄色をベースにした色遣い等変化がありましたがどのような演出・制作過程があったのか、お聞きしたいです。
ジャン=エティエンヌ・ブラ:まず二人の監督について、お互い影響しあっています。ルクレシア・マルテル監督もプリード監督に大いに影響を与えていて、今回の『ラ・ハウリア』の資金集めの時に、作品の絵コンテのようなものを出資者に見せていくのですけれど、その時に使ったのがルクレシア・マルテル監督の『沼地という名の町』という映画の1シーンでした。プールが出てくる映画なので、今回の作品のプールとも繋がっているのですが、そういう意味で二人の監督は、お互い大いに影響を受けていました。色に関してですが、本作はやはり少年たちが多くの暴力などの苦難を抱えて生きている、その苦しさというのをもちろん描きたかったのですけれども、監督が最後に伝えたかったメッセージというのは、誰でも変わる可能性がある、暴力の負のスパイラルから抜け出すことができる、ということを伝えたかったのだと思います。なので、エンドクレジットのところで希望を与えるような、光が見えるような黄色を選んであえて使用したのだと思います。

ルー・シコト:もう一つ色について付け加えるとすると、アートディレクターとプリード監督、そして撮影監督でカラーパレットを使って、いろんな色の組み合わせを試していました。少年たちが緑の生い茂っているジャングルの中で生活している場面に何が合うか、と考えたときに青、という結論に至ったのだと思います。皆さんお気づきかわからないのですが、ユニフォームの青にも2種類ありまして、一つはより明るめの青ですね、一人でいるときは明るめの青を着ています。もう一つは濃いめの青、これは、全員少年が強制的に着させられているものです。そういう色合いをしっかり考えたうえでのユニフォームの青という選択でした。短編と衣装の青というのは、本当に偶然なのですけれども、まだこの作品を作るとき、マルテル監督のこの短編は見ていなかったので、偶然の一致といえます。
Q:映画の後半にある、車に乗っていた二人の少年が荷台から落ちるというシーンは本当に少年が落ちているのでしょうか?どのように撮影をしたのか、お聞かせください。
ジャン=エティエンヌ・ブラ:撮影でトラックから落ちたのは、少年の二人ではなく、スタントマンです。また、このシーンはカットして撮っていたのではなく、すべて連続して、ワンショットで撮りました。撮り方としては簡単で、カメラマンがトラックに乗って、スタントマンが飛び降りるというやり方です。僕自身の映画撮影の信念として、暴力的なシーンをよりリアルに見せるには、リアルタイムで撮ること、シークエンスショット、一発で撮ることを信念として貫いているので、今回もそのように撮影をしました。そのほうが、彼らがトラックの中でどのように感じているのか、というサスペンスが伝わると思います。
Q:暴力の連鎖といったものを極めて深いテーマにしていながら、この映画では暴力を一切映像的には表現していない、これはどういった理由なのでしょうか?
ジャン=エティエンヌ・ブラ:ラテンアメリカ、特にコロンビアでは、このような麻薬や暴力、お酒などの問題が日々起こっています。そのようなもうすでにわかっていること、わかりきっていることをあえて映画の中で説明する必要はない、と感じたので、暴力的なシーンは排除しました。やはり監督が伝えたかったのは、何世代も続く暴力的な関係をいかに打破していくかというところを今回の作品の目的としていたので、あえて暴力を見せていませんでした。希望、光に焦点を当てたかったということがあります。