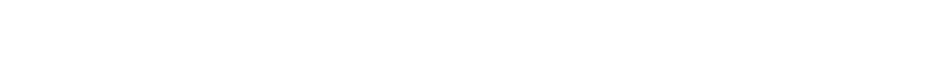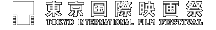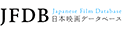チュニジアの鬼才監督、長編デビュー作は黒沢清監督作『CURE』に接点を感じる

ユセフ・チェビ監督
第35回東京国際映画祭のコンペティション部門に選出されたチュニジア・フランスの合作映画『アシュカル』が10月29日、東京・丸の内TOEIで上映され、来日中のユセフ・チェビ監督が観客とのQ&Aに応じた。
本作の舞台は、チュニジア共和国の首都チュニス郊外。民主化運動の最中に工事が中断された建設現場で黒焦げの死体が連続して発見され、ふたりの刑事が捜査を始めるさまを描き出す。上映後、ステージに立ったユセフ監督は本作が長編監督デビュー作。「今回、映画を観に来てくださってありがとうございます。東京に来るのは初めてで、われわれの作品をお見せできる機会をいただいて、温かく迎えてくださって感謝しております」と挨拶した。
撮影が行われたジャルダン・ド・カルタージュは、ジャスミン革命で崩壊したザイン・アル=アービディーン・ベン=アリー政権下で都市化が進められた地域だったが、革命によってその建設は中断。廃虚となった建物で黒焦げの死体が発見されるところから本作の物語は始まる。ガソリンなどが使われた痕跡はなく、自然発火したとしか思えない奇妙な死体だった。だがそうした事件が連続して発生。ふたりの刑事は事件の真相を探ろうと奮闘するが……。
この荒涼としたエリアを「わたしとしては、実はこのエリア一帯、それから廃虚となった建物が映画の主役だと思っています。このあたりはもともとチュニジアでお金を持っている権力者、政権側のために作られた都市部だったんですが、革命で政権が倒れたため、建設が止まっています」と説明したユセフ監督。「母親が祖父からこの土地を相続したので、それをきっかけにこのエリアを知るようになりました。チュニジアの街は、この映画と違って小さくて、通りで触れあったりできるところなのですが、ここはデザインからしてモダンな、ドバイのような大型の道路を擁する場所として作られていました。とてもガランとしていて、人と触れあうことができないような場所なんです。ここに母が家を建てることで、周囲を散策したんですが、なんと奇妙な街なのかと思いました。まるでわたしが廃虚の建物から見つめられている気持ちになり、その奇妙な感じが印象に残ったので、映画を作りたいと思いました」と経緯を明かした。
本作では政治的、寓話的な部分をベースとしながらも、その語り口はフィルムノワール的かつ、ジャンル映画的なものとなっている。ユセフ監督は、「最初のポイントとして、わたしが好きになった映画、そして映画を作るためにはどうしたらいいのかと意識した時に観ていた映画に影響を受けたということがあります。それからロケーションも。このエリアはとても奇妙で、まるで迷路のようだったということで、そこに可能性も感じたんです。この場所ならふたりの警官が犯人を捜そうとしても、なかなか見つけられない。それでここに決めました」と説明する。
さらに、「2つ目のポイントとしては、ジャンル映画、フィルムノワールや警察の映画の様式にすると、ある種の距離感が生まれて、現実的な感じではなくなるということがあります。チュニジアでは政治に触れることはあっても、それを深掘りするということはあまりありません。しかしジャンル映画にすることで、その外側に身を置くことができます。わたしは映画ではリアルに捉えることはできない。ならばしっかりと作った方がいい。そういう意味ではフィルムノワールというものはいい武器になると思います」と明かした。
また、ジャンル映画への思いについて質問されたユセフ監督は、「実は日本の映画、黒沢清監督に影響を受けています」と返答。「プロデューサーから、撮影が始まる1カ月くらい前、準備をしている時に、黒沢清監督の『CURE』を観たと言われて。それで自分も昔に観たことを思い出したんです。脚本を書いている時や、準備をしている時は忘れていたんですが、その後に言われてもう1回観てみると、なんだかストーリーがつながっているような気がした」そうで、「不思議なキャラクターが出てきて、人を洗脳して、犯罪を犯すまでに至る。黒沢監督のリズム感、スタイル、テンポともにすばらしい作品だと思いました。明確に意識したというわけではないですが、プロデューサーから『CURE』の話が出た時は、どこかで接点を感じましたね」と振り返った。ちなみに好きな映像作家としては、ロベール・ブレッソンとブリュノ・デュモンの名前を挙げていた。
第35回東京国際映画祭は、11月2日まで日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区で開催。
新着ニュース