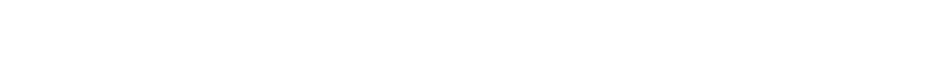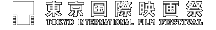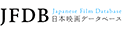「深田監督の作品を見て、劇映画を撮りたい思いが湧いてきた」ツァイ・ミンリャン監督が深田晃司監督とトーク

深田晃司監督とツァイ・ミンリャン監督
第35回東京国際映画祭と国際交流基金による共同トークイベント「「交流ラウンジ」深田晃司×ツァイ・ミンリャン」が10月29日に開催され、深田晃司監督と台湾のツァイ・ミンリャン監督が互いの作品や、日台の映画事情について語り合った。
深田監督の3作品『ほとりの朔子』(13)、『淵に立つ』(16)、『海を駆ける』(18)を鑑賞したというツァイ監督は「どれも素晴らしかったです。深田監督の映画手法、言葉の使い方が私によく似ており、同じ根を持つと思いました。私はこの数年、劇映画を撮っていなかったのですが、深田監督の作品を見て、また劇映画を撮りたいという思いが湧いてきました」と伝える。
深田監督は感激の面持ちで、「ツァイ監督の作品はいち映画ファンの頃から見ているので、自分自身の作品を見ていただけるだけでもうれしいです。ツァイ監督の作品や発言を通して、自分も共通することが多いと思っていました。『青春神話』から研ぎ澄まされて、物語を語るために映像もセリフも消費されていないのが素晴らしい。私はエリック・ロメールが好きで、ロメールいわくセリフとは「必要なセリフと本当のセリフに分かれる」と。物語を進めるためのセリフは不自然で、消費されないセリフが重要になるということです。ツァイ監督の映画は物語を進めるためのセリフが排除されています」とツァイ監督の作品の特徴を挙げる。
深田監督の見解を受け、ツァイ監督は「私の映画は沈黙が多いのです。登場人物その人が孤独で寡黙だからです。私が映画で大事にしているのが感受性。この感覚がどのように観客に伝わるのか、本当にこういう人がいると思ってもらえるような人物造形です。また、音楽が登場人物の心情を過度に表現するのを恐れているので、私の作品では音楽が少ないのです。ですから、私は基本的なリアリズム作家だと言えるでしょう。そして、私の映画の中にはシュールな雰囲気が登場します。生活の中にシュールな瞬間があるのです。そこを切り取って、表現しています」と解説。
さらに、深田監督作に触れ「特に深田監督の『淵に立つ』はリアルな人達だと思いました。夫婦関係や家庭状況を描くための食卓の動作、しゃべり方など非常にリアルさを感じました。特に食事の場面で、その食べ方が人物を表現するのに重要です。浅野(忠信)さんが現れてから、雰囲気が一変します。それがすごくうまい。こういう雰囲気を作るために一回物語に引き込むのです。物語は劇的に進みますが、すべてが非常にリアル。心に響く作品でした。この映画は観ていた私に、こういう物語、人物があると信じさせてくれました。各人物が持つ内在的なものに深く共感しました」と称えた。
「うれしくて言葉が出ません」と喜ぶ深田監督は、「演技について、人物のリアリティについて語ってくださったのがとてもうれしい。それは、私ひとりの力ではなく、俳優の力があるからです。監督のイメージを通しすぎるのではなく、俳優が作っていく。私は観客のために演じるのではなく、共演者と日常のように向き合ってほしいとお願いしています」と、俳優の重要性やかかわり方についてツァイ監督に質問した。
「私は俳優との交流はあまりありません。私が大事にしたいのは、人物が演じている空間です。その雰囲気を役者に提供してあげることが重要です。私の映画はセリフに頼って物語を進行していく作品ではありません。役者は空間と向き合ってどう演じるかが一番重要です」(ツァイ)
そして、自作『愛情萬歳』などの例を挙げ、「映画製作で一番難しいのが俳優にどう演じてもらうかということ。そこがうまくいかないと映画にならない。深田さんはそのバランスをうまく心得ていると思います。それは『ほとりの朔子』を見ても思いました」とコメントした。
ベネチア、ベルリンで受賞経験を持つツァイ監督、深田監督も『淵に立つ』がカンヌ受賞、最新作『LOVE LIFE』がベネチアのコンペ出品と、両監督ともにその作家性が世界の映画祭で高く評価されているが、興行的にはなかなかふるわない状況にあるとそれぞれが明かし、日台の映画界についての話題に移行した。
ツァイ監督はホウ・シャオシェン監督、エドワード・ヤン監督らが世界に大きな影響を与えた時代とは変わってきており、「最近の台湾映画は商業的なジャンル映画に偏ってきて、マーケット的には賑わいは見せていますが、以前のような輝きは失われていると思う」と報告。「しかし、日本は深田監督や濱口竜介監督のよう優れた監督が出てきたのが素晴らしい。深田監督は個人の創作の道を突き進んでると思います。独特の言語表現を模索し、活力のある映画にしていると思います。それが映画にとって、興収とはかかわりがないところで一番大事なのです。売る映画を作るのはある種簡単なことで、本当の意味で創作力のある作品を作るのは難しい。その意味でも日本は映画強国として成り立っているのでは」と語る。
そして、自身と俳優とで街に立ち、チケット1万枚をあらかじめ手売りして劇場と上映期間をキープしたり、美術鑑賞の習慣や文化が根付いているヨーロッパを例に挙げ、アート映画を見る観客を育てるために、美術館での上映するなど、様々な試みを行ったことを深田監督に伝えた。
フランスをはじめ海外でも自作が公開されている深田監督は、「フランスでも、興収ランキングではもちろん娯楽映画が多くを占めますが、よくわからないけれど外国から来た作品を見てみようと思う層が多い。自分の作品も日本よりフランスの方がお客さんが入っていて、国内の期待値に応えられない一方で、海外配給が決まっていくと悩んでしまいます」と吐露。そして、「フランスは学校で映画の授業で小津を見るそうです。そうやって、(外国映画や非商業的な映画を見る)お客さんが育っていていると思う。まずはコツコツと作りたいものを作って、お客さんを増やすのが大事」と持論を述べた。
「爆発的にヒットした経験は私はありません。しかしそういう状況であっても、満足しています。一作一作大好きな作品なので。賞味期限が長い作品を作っていて、今、アメリカでも配給されています。深田さんも私と同じ道を歩んでいるのではないでしょうか」(ツァイ)、「自分の映画もそうあってほしいと思っています。80年代の作品が最近フランスでの配給が決まったので、撮っていてよかった。細く長く見られて欲しい」(深田)と、志を同じくする両監督は共感し合い、固い握手を交わした。
新着ニュース