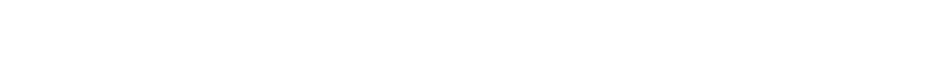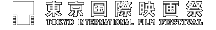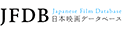東京国際映画祭公式インタビュー:『エゴイスト』松永大司監督

コンテンポラリーアーティストで、トランスジェンダーであるピュ~ぴるを追ったドキュメンタリーが公開されたのが2011年。松永大司監督は、それ以降、順調に映画を制作していく。
15年に公開された『トイレのピエタ』は数々の映画賞を受賞し、村上春樹の短編小説を映画化した『ハナレイ・ベイ』(18)は、吉田羊を主演に据え、ハワイの風景と相俟って美しい映画となった。
新作『エゴイスト』は、ファッション誌の編集者として活躍している浩輔(鈴木亮平)が主人公だ。14歳で母を亡くし、ゲイである事を押し殺して思春期を送ってきた。そんな彼がある日、シングルマザーである母を支えながら、パーソナルトレーナーとして働く、龍太(宮沢氷魚)と知り合う。惹かれ合ったふたりは、満ち足りた時間を重ねていく…。
高山真の小説「エゴイスト」を、映画は、物理的に精神的に、愛の形を多様に映し出す。
――原作を読まれて、映画化したいと思ったポイントはどんなところだったのでしょうか。また、この原作との出会いは?
松永大司監督(以下:松永):この映画の企画プロデューサーでもある明石(直弓)さんに、この原作で映画を撮ってみませんかと言われたのが、最初のきっかけです。彼女と出会ったのは、僕のデビュー作であるドキュメンタリー映画『ピュ~ぴる』の公開直後くらいでした。既に観てくれていて、「面白かった」と言ってくれました。その時、いつか一緒に映画を撮りたいという話をしました。
『ピュ~ぴる』もジェンダーやセクシュアリティが関係していたし、この原作にはそれ以外のテーマもあって、非常に興味深いと思ったのです。
――それ以外のテーマというのは「愛は身勝手か」というものですか?
松永:同性愛も重要なテーマではありつつ、もうちょっと広い意味で、他者との愛において、家族の愛というものをどう捉えるかというのがテーマだったので、面白いなと思いました。
――浩輔役は最初から鈴木亮平さんが候補だったのか、それともオーディションがあったのか教えてください。
松永:キャスティングに関して、今まで作った映画も、全部プロデューサーと一緒に相談しながら決めています。今回は、浩輔役の鈴木亮平さんと龍太役の宮沢氷魚さん、その母親役の阿川佐和子さん、その主要な3人のバランスを気にしました。
――鈴木さんも宮沢さんも身長が高いですよね。真ん中に阿川さんを置いて、劇中、みんなで写真を撮る時の構図が興味深かったです。
松永:偶然ですが、自分が一緒に仕事をさせてもらう人はみんな身長が高い。でも、背が高い人が単にいいのではなく、背格好も含めてキャラクターだと思うのです。
――浩輔が仲間たちと飲んでいる居酒屋のシーンは、かなりドキュメンタリーっぽい感じもしました。
松永:全編を通して、今回、ほぼ手持ちでワンシーンワンカットで撮っています。あのシーンは、20分を3~4セット、ワンシーンワンカットで撮っています。
クランクイン前からカメラマンとそういうスタイルでやりたいと、話していました。リハーサルで実際のカメラを使って撮って、それを軽く編集し、試写室でラッシュしてから撮影に臨みました。
――そこまで念入りに。
松永:はい、そこまで。まあ、ここまでしっかりとやったのは今回が初めてですけれど。でも基本的には、毎回カメラテストをやって、スクリーンでラッシュしてからクランクインしていますね。日本映画って撮影に入ると、バーっと突き進んでいくので、撮り方を撮影場でディスカッションするよりは、自分は演出に集中したいので。

――そこまでやる監督はあまりいないのでは?
松永:僕は助監督の経験が少ないから、他の方がどうやっているかは分かりませんが、僕なりのスタイルで実践させてもらっています。もし、助監督で長年現場に入っていたらやり方も違ったかもしれません。常に自分なりのベストを模索しながらやっています。
――ファッション誌の編集者だからというのもあると思いますが、主人公はクローゼットに沢山の衣装があります。あれは監督自らの指示ですか。はっきり映らない部分もあるから分からないかもしれないと…。
松永:分かる人には分かる事をやらないといけない。もちろん、予算と時間が限られている中で、全て100%のディテールが出来ない時もあります。けれど、浩輔というキャラクターを作るにあたって、身につけているものはすごく大事でした。それは洋服だけでなく、他も出来る限りの事はやろうと思いました。
――先程、浩輔と仲間たちのシーンをドキュメンタリー的だと言いましたが、鈴木さんも演技にノッて楽しそうでした。
松永:そうですね。俳優が演技をするというのは、台詞があって動きが決まっていく中で自然にやるのですが、時に即興芝居のようにリアルなリアクションを取っていくという事も、僕は結構好きなのです。
どうやったら形にできるかと、この『エゴイスト』では挑戦しましたね。
――『トイレのピエタ』『ハナレイ・ベイ』、今回もそうですが、死が身近にあるというか、そんな感じがして。その辺り意識されていますか?
松永:自分で作っておきながら、確かに毎回人の死があると今、思いました。
「死」はテーマにとして扱うには絶対的すぎて、時にマイナスの方に転がることがあります。僕自身も、死を身近に感じる経験が小さい頃からあったりしました。
人が亡くなるというのは、特別ではあるのですが、実は特別ではないとも思っています。その死に対して、自分たちがどう向き合うか。
作品で言うと、悲しいところで終わるのではなく、残された人にプラスに働く事があるといいのではないか。理想論かもしれませんが、人の死を悲しいという事で終わらずに、時間が経って残された人が、それをポジティブなものとして捉える要素があると信じたい。
――今回の映画を、どう観てもらいたいですか?
松永:『ピュ~ぴる』が様々な映画祭に招待され訪れた際、ジェンダーやセクシュアリティに関する捉え方が国によって違いましたし、日本の状況は世界に比べてだいぶ遅れているとも感じました。
当時のそういう思いから、この『エゴイスト』はセクシュアリティに関しても、しっかりと正面から向き合ったので、観客や審査員の方にどう映るのかとても興味深いです。
それは海外の審査員だけでなく、日本の観客に関しても言えます。この映画をきっかけに、それぞれの考え方での議論が出てくるようになったらいいなと思います。
――今回、コンペに出品されている3監督の登場人物は、普通より少し違ったところにいる人物を捉えていると思います。普通って何かとか、言葉が難しいのですが。
松永:映画はエンターテイメントでありますが、そこに社会性も含めたメッセージを伝えられるものだとも思っています。この世界には知らないという事が原因で、無意識や無自覚に差別をしていたりする。だから今作を観てくれた方に、知らないことを知ってもらえたり、考えるきっかけになったら嬉しいです。差別をしようと思ってする人はほとんどいないはずです。それでも差別が起こってしまうことが、難しいなと思います。
――最後に、やはり愛はエゴですか?
松永:それは究極的だし、僕が言ってしまってはいけない気がする(笑)。
ただ、この原作をやろうと思ったひとつの大きな理由に、阿川さん演じる妙子が、「受け取った私たちが愛だと感じているから、それでいいんじゃない」と言うセリフがあります。このセリフを読んだ時、とても心に響きました。一番大事なのは、当事者がどう思っているかということです。今の世の中は関係のない人が誰かの行為について、あれやこれや言いますよね。当事者同士でしか分からない事があって、それを他者が結論づけるのはよくないことです。
今の世界ってすごく息苦しい。漂白されたような白を求められる感覚があります。潔癖というか。
鈴木亮平が演じる主人公の愛のあり方は、観客の全員が共感出来るかどうかは分からないですが、それを愛だと思っていればいい。他人が、「あなたの愛はエゴだ」と結論づけることはしてはいけない。
――実は観ていて、全然エゴイストだとは思いませんでした。でもタイトルに戻ると、ああ、エゴイストという考えもあるのかと。
松永:「エゴイスト」という意味をもう一回考えてみて欲しい。そんな意味も込めて映画の最後にもう一度タイトルを出しました。この言葉はとてもネガティブなイメージを感じますが、映画を観見終わった時、主人公のこの愛の注ぎ方を、あなたは否定できますか?と。エゴイストという言葉の意味合いが、ちょっとでも変わる可能性はあるのかなと思っています。

インタビュー/構成:東京国際映画祭 小出幸子
第35回東京国際映画祭 コンペティション部門
『エゴイスト』

監督:松永大司
キャスト: 鈴木亮平、宮沢氷魚、阿川佐和子