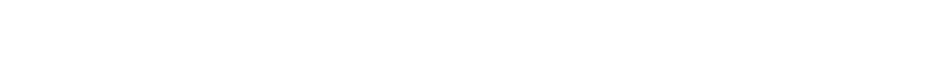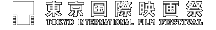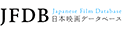第35回東京国際映画祭のコンペティション部門には、3本の日本映画が選出されている。今泉力哉監督が手掛けた『窓辺にて』、福永壮志監督による『山女』、松永大司監督の『エゴイスト』。9月21日に行われたラインナップ発表会見では、作品、そして映画祭への思いを口にしていた監督陣。今回、東京国際映画祭開幕を前に、その思いをさらに掘り下げるべく、てい談という形式で語り合ってもらった。
●これまでの東京国際映画祭について――今泉監督の印象は?
まず話題にあげたのは“これまでの東京国際映画祭”について。今泉監督にとっては『サッドティー』『知らない、ふたり』『退屈な日々にさようならを』で参加した日本映画スプラッシュ部門、『愛がなんだ』で選出されたコンペ部門(第31回)など、東京国際映画祭は馴染み深い場所だ。
今泉監督「海外の映画祭に参加できていない時から、海外の作品と一緒の機会に上映してもらい、色々な方々に観ていただく――そんな場に初めて選んでいただいたような映画祭で、(元プログラミングディレクターの)矢田部(吉彦)さんとの出会いも含め、良い経験をさせていただいたなという思いがあります。その一方で、アジアの映画祭において“どの位置にいるのだろうか”という点を真剣に考えてしまうこともありました。どういう立ち位置になっていくのか――これは実際に参加している側から見ても、ひとつの課題だと思います」
かつてコンペ部門に選出された『愛がなんだ』。「プログラマーの説明では、芸術性と商業性の両方が必要で一般の観客にも通じるものでなければならないということだったが、その2つは組み合わせることはできないと思っている」という意見を投じた審査委員長ブリランテ・メンドーサ監督は、同作に「商業的で観客が共感しやすい内容だが、本来であればコンペに出る作品ではないと思う」といった評価を下している。
今泉監督「もちろん評価してくださる方もいたので、メンドーサ監督の意見がすべてではありません。でも、色々なことを考えましたよね。コンペに選ばれたという単純な喜びだけでは片づけられない複雑な部分があると思います。今回も『愛がなんだ』と同様に恋愛モノのオリジナル映画。どういう状況、どのような見られ方をされるのか――その点を冷静に見ています」

『窓辺にて』(今泉力哉監督作)
©2022「窓辺にて」製作委員会
●東京国際映画祭は初参加 福永監督「映画祭のカラーは見えにくかった」
『リベリアの白い血』『アイヌモシリ』(※タイトルの「リ」は小書き文字が正式表記)などで知られる福永監督は、東京国際映画祭初参加となった。作り手&観客としても、あまり馴染みがない映画祭だったようで「外から見た印象は“(日本映画界における)一番大きなイベント”。今泉監督が仰ったように、映画祭の方向性という観点では不明瞭なところがあったと感じていました」と指摘する。
福永監督が以前から気になっていたのは、日本で公開される作品のプロモーション要素が強かった特別招待部門。第34回からプログラミングディレクターに就任した市山尚三氏は、同部門の名称をガラ・セレクションに変更。ショーケース的な側面の排除に踏み切っている。
福永監督「映画祭のカラーが見えにくくなり、あまりよくないのではないかと思っていました。市山さんが指揮を執るようになり、その要素が薄まったという点は、非常に良いことだと思います。今回のラインナップを見てみると、アジアに重きを置いているような印象があります。そういう意味でも、新しい方向に踏み出しているというものを感じますよね」

『山女』(福永壮志監督作)
©YAMAONNA FILM COMMITTEE
●まずは目指したくなる場所へ 松永監督が期待している映画祭としての機能
松永監督は、国際交流基金アジアセンターと東京国際映画祭の共同プロジェクト『アジア三面鏡2018 Journey』への参加を経て、コンペ部門に初めて選出されている。
松永監督「一般の客として来ていた時の印象は、なかなかチケットが取れないというもの(笑)。ワールド・フォーカス部門を狙って、チケットを取りにいっていましたね。一方で、本来は大勢の人たちに観られるべき『アジアの未来部門』等への誘導が、映画祭として機能していなかったように思います」
東京国際映画祭は、日本で最も規模の大きい映画祭である。だからこそ「韓国の監督であれば、まずは釜山国際映画祭を目指したいと考える。同様に、日本の若い人たちが“まずは目指したくなる”。そういうステータスを持った映画祭になることが理想的」と話す松永監督。
松永監督「映画監督であれば、カンヌ、ベルリン、ベネチアに行きたいと誰もが思うはず。でも、日本の映画祭を飛ばして、いきなり海外の映画祭に選出されるというのは、誰もができることではありません。キャリアとともにステップアップしていけばいいと思うんです。だからこそ、東京国際映画祭には、日本の映画監督が自作を発表したくなる場として機能してほしいと思っています。こんなにも大勢の方々に、作品を鑑賞してもらうことができる機会なんですから」

『エゴイスト』(松永大司監督作)
©2023 高山真・小学館/「エゴイスト」製作委員会
●“交流の場”という視点から語る映画祭
今年のコンペ部門は2022年1月以降に完成した長編映画が対象となり、107の国と地域から1695本の応募があった。舞台演出家で映画監督のジュリー・テイモアが審査委員長を務め、シム・ウンギョン(俳優)、ジョアン・ペドロ・ロドリゲス(映画監督)、柳島克己(撮影監督)、マリークリスティーヌ・ドゥ・ナバセル(元アンスティチュ・フランセ館長)が審査員として参加。コンペティション部門の全15作品を審査する。
来日する監督陣との“交流”に期待を寄せている福永監督。「コンペは映画祭を代表する部門ですし、映画祭自体を知るためにも、なおさら選出された作品は観ようと思っていました。加えて、来日した監督たちと交流することができるかもしれない――これは映画を作った自分へのご褒美でもありますよね。これも映画祭の良いところのひとつです」。今泉監督、松永監督にも“交流”という視点から、東京国際映画祭について語ってもらった。
今泉監督「日本映画スプラッシュ部門で知り合った監督は、ある種ライバルのような関係。その人たちがいたから、次の作品を作ることができた。そんな人たちとたくさん出会っています。特に、渡辺紘文監督が日本映画スプラッシュ部門のグランプリ(『プールサイドマン』)を獲った時なんかは、俺が一番喜んでいたんじゃないかな(笑)。逆に同世代の深田晃司監督が審査委員を担当されていた時は悔しさを感じたりすることも。良い刺激を受けていました」
松永監督「良い出会いになったのは、『アジア三面鏡』で知り合ったエドウィン監督ですね。僕は日本に住みながら映画を作っていますが、キャスティングやクルー、出資面に関しては、日本以外でも取り組んでみたいなと思うことがあるんです。例えば、コンペで出会う監督たちとは『僕があなたの国に行ったらサポートして欲しい。代わりに、日本で撮影を行う場合は協力する』といったコミュニケーションがとれたらいいなと。映画祭は、参加したら終わりではなく、あくまで“過程”だと思っているんです』
福永監督「日本の宣伝における映画祭の扱われ方について、個人的に思っていることがあります。映画祭に出品したという事実だけを“スタンプ”のように利用し、日本での配給の勢いに使う。これが最大の目的のようになっているような印象を受けるんです。本来の映画祭は、監督同士で交流し、そこでの経験を持ち帰り、次へと繋げていく場所だと思うんです。祝いの場でもあり、映画文化を広めるために、さまざまなことを共有する場でもあります』
今泉監督「俺、英語が喋れないんですが、だからこそ英語を話せるスタッフの方が、要所要所で傍にいてくれるといいのかもと思いました。それは頼めばできることなのかもしれないけど、これまで積極的にお願いをすることはなかった。せっかく“交流”できる場なのに、結構損をしていますよね。もちろん自分が喋れるようになるのが一番良いんですけど……。海外の映画祭に行った時、『このタイミングで、あの人と喋れないのはもったいない……』なんて悔しく感じることが何度もありましたから」
●日本で一番大きな映画のイベント=今の日本映画界のイメージに深く関わる
続けて、松永監督は「映画祭は“過程”である」という発言を、さらに掘り下げていく。
松永監督「映画祭は、マーケットの場でもありますよね。日本のプロデューサーには『この映画を海外に売っていく』という意識が、まだ低いような気がしています。僕らは人生をかけて、映画を作っているわけです。映画祭は、発表の場としても機能し、作品に関わった人々の“その後の人生”にも大きく関わっていく。『そこまで課すのは、暑苦しい』と言われてしまうかもしれませんが、そうあるべきだと思うんです。ひとつひとつ変化をしていかなければ、日本映画や東京国際映画祭の在り方は変わっていかない。コンペに入ったことで、ようやくこういうことが言える立場になったのではないかと思っています。日本人監督として、この国の一番大きな映画祭とどう向き合っていくべきなのか。ここには、責任があるのではないかと考えています」
今泉監督「福永監督が仰った“スタンプ”の話は、日本の映画が国内を向き過ぎてしまっているという面もありますよね。作り手も、宣伝や配給側も“国内で完結”という意識であれば、それ以上は絶対に広がっていかない。もちろん作品を過信したり、過剰に評価するべきではなく、あくまで冷静に判断するべきではあります。ただ、これまでの東京国際映画祭でも、コンペや他部門に選出された作品が、さまざまな国の方の目に触れたことで、世界に羽ばたいていった事例がたくさんあります。どう広げていくべきなのか――これを作品に関わる人たちが考えているか、考えていないかで結果は異なるはず」
福永監督「映画祭は、さまざまなことを発信して、映画文化全体への理解を深めることができる場でもありますよね。日本で一番規模の大きい映画祭が、しっかりとした“映画祭のモデル”になることで、広がる効果ってたくさんあると思うんです。それに、海外からいらっしゃる方にとっては、今の日本の映画界の印象にも直結しますよね。『日本で一番大きな映画のイベントは、こういうものなのか』と。このイメージは、現在の日本映画業界の印象に深く関わってしまう。そういう意味でも内だけを見るのではなく、外に向かっていくということは大事なのかもしれません」
●宣伝&メディアの在り方とは?「それぞれの持ち場で意識を変えるべき」
監督陣の議論は、作品を巡る宣伝、メディアの在り方にも展開していった。
松永監督「日本の宣伝というものは、『こういう映画だから、こんな宣伝にしましょう』とベルトコンベア式に流れているような印象を受けています。そこも変わっていかないとダメだと思います。作り手の表現や認識は、時代に合わせて変わっていかないといけないと言われて、色々なことを課されながらも、そのなかで試行錯誤しながら作っている。そうして、作った後、劇場で上映されるまでの手法というものが、恐ろしいほど変わっていません。その点も、映画祭の在り方と深く関わっているように思えるんです。なるべく宣伝にも意見するようにはしていますが、僕ら監督にも限界というものはあります。宣伝に携わる方たちが、どのように東京国際映画祭を良い意味で利用するのか。皆がそれぞれの持ち場で意識を変えていかないと」
今泉監督「“大きい話”になってしまいますが、『映画というものを、今の日本の映画業界、マスコミがどうとらえているのか』という部分にまで戻ってしまうのかもしれませんよね。商業的・興行的な部分は、もちろん無視できないものです。しかし、本当に内向きな作品が圧倒的に多い。見やすさやテンポなどを求められることも多々あります。製作した映画を、関わった人々がどう思っているのか――この意識次第で、見せ方も変わってくる気がしています。例えば『三大映画祭の受賞作品は、ヒットするのか?』という点にも繋がってきますよね」
松永監督「日本の興行では“良い映画がヒットする”とは言えず、カンヌ、ベルリン、ベネチアで高評価を得た作品も、日本で観てもらえるかと言えば、決してそうではない。その一方で“三大映画祭の評価が全て”かといえば、それも違うはず。日本のマーケットの特殊性というものは、かなりあると思います。だからこそ、どう上手く宣伝していくのかが重要です。それと、今回のラインナップ会見、首を傾げてしまった光景があるんです。それは、メディア向けのQ&A。思ったよりも質問が出なかったですよね?」
今泉監督「海外の映画祭では、あまり見ない光景ですよね」
松永監督「そう、海外の映画祭であれば、制限時間ギリギリまで質問を投げかけられることが多いですよね。事前のインフォメーションが少なかったという、仕方のない部分もあるとは思いますが……例えば、僕が映画専門の記者をしているのであれば、過去作を引き合いに出しつつ、新作ではどのようなアプローチを行ったのかといった質問を投げかけると思います。ラインナップ作品、映画祭そのものについて、さまざまな角度で興味をもってもらえるよう、積極的に関わっていただきたいです」
福永監督「監督の立場から見た時に『それは間違っているのではないか』と感じてしまう部分を、映画祭という場では、可能な限り無くして欲しいという思いがあります。例えば、舞台挨拶におけるバラエティ番組のようなトーク。肝心の映画の話がまったくできないという場合が多々ある。映画に特化したサイトでも、映画自体に関係のない部分を強調してしまうことがありますよね。映画祭として様々な面において“良いモデル”を発信できれば、映画業界全体に良い影響を与えてくれるのではないかと思っています」
今泉監督「そもそもマスコミが映画に興味がないんですよね。いや、興味があってもそれを発信できにくい土壌が当たり前になってしまっていて、俳優の話などだけが取り上げられることが多い。これはつくり手の責任でもあるけど、日本における映画の置かれている位置、立場を本当に変えていきたいし、それを手伝ってほしいです、切に」
●これからの東京国際映画祭について――日本映画に対して「まだ諦めていない」
手掛ける映画のタイプは、それぞれ異なったもの。しかし、日本映画に対して共通の思いを抱えている――松永監督は、今回のてい談を通じて、そう確信したようだ。
松永監督「こうやって3人で話をさせて頂いて感じたことは、僕たちは日本映画に対して『まだ諦めていない』というもの。『松永、しょうがない。日本映画はこういうものだから』。そんな寂しい言葉を上の世代から聞くこともありました。長年、悔しい思いをし続け、闘えば疲弊していくというのもわからなくもありません。それは、生きていくための術なのかもしれません。でも、今ここにいる3人は、諦めていないんですよね。自分の映画だけでなく、日本の映画そのものについて『もう少しこうあるべきなのではないか?』と言い続けたい。“言葉を発する”というのは、結構しんどいことなんですけどね。
今泉監督「言葉というものは、自分自身に返ってきてしまいますからね」
松永監督「そうなんです。何かを発信しようものなら『では、お前はどうなんだ? 面白い映画を作れよ』と言われてしまう。でも“諦めていない人たち”がコンペに選ばれたというのは、映画祭が変わっていく兆候のひとつなんじゃないかと。今泉監督も福永監督も、まだまだ言いたいことはいっぱいあるはず。そういう人たちがいることは、ひとつの希望のような気がしています。
今泉監督「松永監督、福永監督のように、しっかりと海外を視野に入れた人がコンペに選ばれたという事実は、今回大きいことなんじゃないかなと思います。これまで思ってはいたけれど、なかなか言葉にすることが出来なかった――そんなことをいっぱい聞けたような気がしていて。そこに感動しています」
松永監督「東京国際映画祭は、海外の主要な映画祭と比べると『レベルが低い』と思う人もいるかもしれません。でも、コンペティション部門に関していえば、日本映画がグランプリを獲ったのは2回だけ(第1回『台風クラブ』相米慎二監督、第18回『雪に願うこと』根岸吉太郎監督)。かなり現実的な結果を突きつけられているんです。だからこそ、日本の映画が“本気で賞を獲りにいく”という気持ちで参加することが、東京国際映画祭を変える要素のひとつになる。この意識が、かなり必要なことだと思っています。その前提で他国と競い合い、メインの賞に絡んでいく。それが出来てくれば、映画祭の見られ方というものも変わっていくのかもしれない。審査委員は、海外の方が中心ですし、そこにはなんの忖度もない。日本だろうが、海外だろうが、平等に映画を観てくれますから。“良質”の中で競い合っている――そんな見られ方がされるようになればいいなと思っています」
第35回東京国際映画祭は、10月24日~11月2日、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区で開催。オープニング作品『ラーゲリより愛を込めて』(瀬々敬久監督)で幕を開け、クロージング作品には『生きる LIVING』(オリバー・ハーマナス監督)が控えている。

第35回東京国際映画祭のコンペティション部門には、3本の日本映画が選出されている。今泉力哉監督が手掛けた『窓辺にて』、福永壮志監督による『山女』、松永大司監督の『エゴイスト』。9月21日に行われたラインナップ発表会見では、作品、そして映画祭への思いを口にしていた監督陣。今回、東京国際映画祭開幕を前に、その思いをさらに掘り下げるべく、てい談という形式で語り合ってもらった。
●これまでの東京国際映画祭について――今泉監督の印象は?
まず話題にあげたのは“これまでの東京国際映画祭”について。今泉監督にとっては『サッドティー』『知らない、ふたり』『退屈な日々にさようならを』で参加した日本映画スプラッシュ部門、『愛がなんだ』で選出されたコンペ部門(第31回)など、東京国際映画祭は馴染み深い場所だ。
今泉監督「海外の映画祭に参加できていない時から、海外の作品と一緒の機会に上映してもらい、色々な方々に観ていただく――そんな場に初めて選んでいただいたような映画祭で、(元プログラミングディレクターの)矢田部(吉彦)さんとの出会いも含め、良い経験をさせていただいたなという思いがあります。その一方で、アジアの映画祭において“どの位置にいるのだろうか”という点を真剣に考えてしまうこともありました。どういう立ち位置になっていくのか――これは実際に参加している側から見ても、ひとつの課題だと思います」
かつてコンペ部門に選出された『愛がなんだ』。「プログラマーの説明では、芸術性と商業性の両方が必要で一般の観客にも通じるものでなければならないということだったが、その2つは組み合わせることはできないと思っている」という意見を投じた審査委員長ブリランテ・メンドーサ監督は、同作に「商業的で観客が共感しやすい内容だが、本来であればコンペに出る作品ではないと思う」といった評価を下している。
今泉監督「もちろん評価してくださる方もいたので、メンドーサ監督の意見がすべてではありません。でも、色々なことを考えましたよね。コンペに選ばれたという単純な喜びだけでは片づけられない複雑な部分があると思います。今回も『愛がなんだ』と同様に恋愛モノのオリジナル映画。どういう状況、どのような見られ方をされるのか――その点を冷静に見ています」

『窓辺にて』(今泉力哉監督作)
©2022「窓辺にて」製作委員会
●東京国際映画祭は初参加 福永監督「映画祭のカラーは見えにくかった」
『リベリアの白い血』『アイヌモシリ』(※タイトルの「リ」は小書き文字が正式表記)などで知られる福永監督は、東京国際映画祭初参加となった。作り手&観客としても、あまり馴染みがない映画祭だったようで「外から見た印象は“(日本映画界における)一番大きなイベント”。今泉監督が仰ったように、映画祭の方向性という観点では不明瞭なところがあったと感じていました」と指摘する。
福永監督が以前から気になっていたのは、日本で公開される作品のプロモーション要素が強かった特別招待部門。第34回からプログラミングディレクターに就任した市山尚三氏は、同部門の名称をガラ・セレクションに変更。ショーケース的な側面の排除に踏み切っている。
福永監督「映画祭のカラーが見えにくくなり、あまりよくないのではないかと思っていました。市山さんが指揮を執るようになり、その要素が薄まったという点は、非常に良いことだと思います。今回のラインナップを見てみると、アジアに重きを置いているような印象があります。そういう意味でも、新しい方向に踏み出しているというものを感じますよね」

『山女』(福永壮志監督作)
©YAMAONNA FILM COMMITTEE
●まずは目指したくなる場所へ 松永監督が期待している映画祭としての機能
松永監督は、国際交流基金アジアセンターと東京国際映画祭の共同プロジェクト『アジア三面鏡2018 Journey』への参加を経て、コンペ部門に初めて選出されている。
松永監督「一般の客として来ていた時の印象は、なかなかチケットが取れないというもの(笑)。ワールド・フォーカス部門を狙って、チケットを取りにいっていましたね。一方で、本来は大勢の人たちに観られるべき『アジアの未来部門』等への誘導が、映画祭として機能していなかったように思います」
東京国際映画祭は、日本で最も規模の大きい映画祭である。だからこそ「韓国の監督であれば、まずは釜山国際映画祭を目指したいと考える。同様に、日本の若い人たちが“まずは目指したくなる”。そういうステータスを持った映画祭になることが理想的」と話す松永監督。
松永監督「映画監督であれば、カンヌ、ベルリン、ベネチアに行きたいと誰もが思うはず。でも、日本の映画祭を飛ばして、いきなり海外の映画祭に選出されるというのは、誰もができることではありません。キャリアとともにステップアップしていけばいいと思うんです。だからこそ、東京国際映画祭には、日本の映画監督が自作を発表したくなる場として機能してほしいと思っています。こんなにも大勢の方々に、作品を鑑賞してもらうことができる機会なんですから」

『エゴイスト』(松永大司監督作)
©2023 高山真・小学館/「エゴイスト」製作委員会
●“交流の場”という視点から語る映画祭
今年のコンペ部門は2022年1月以降に完成した長編映画が対象となり、107の国と地域から1695本の応募があった。舞台演出家で映画監督のジュリー・テイモアが審査委員長を務め、シム・ウンギョン(俳優)、ジョアン・ペドロ・ロドリゲス(映画監督)、柳島克己(撮影監督)、マリークリスティーヌ・ドゥ・ナバセル(元アンスティチュ・フランセ館長)が審査員として参加。コンペティション部門の全15作品を審査する。
来日する監督陣との“交流”に期待を寄せている福永監督。「コンペは映画祭を代表する部門ですし、映画祭自体を知るためにも、なおさら選出された作品は観ようと思っていました。加えて、来日した監督たちと交流することができるかもしれない――これは映画を作った自分へのご褒美でもありますよね。これも映画祭の良いところのひとつです」。今泉監督、松永監督にも“交流”という視点から、東京国際映画祭について語ってもらった。
今泉監督「日本映画スプラッシュ部門で知り合った監督は、ある種ライバルのような関係。その人たちがいたから、次の作品を作ることができた。そんな人たちとたくさん出会っています。特に、渡辺紘文監督が日本映画スプラッシュ部門のグランプリ(『プールサイドマン』)を獲った時なんかは、俺が一番喜んでいたんじゃないかな(笑)。逆に同世代の深田晃司監督が審査委員を担当されていた時は悔しさを感じたりすることも。良い刺激を受けていました」
松永監督「良い出会いになったのは、『アジア三面鏡』で知り合ったエドウィン監督ですね。僕は日本に住みながら映画を作っていますが、キャスティングやクルー、出資面に関しては、日本以外でも取り組んでみたいなと思うことがあるんです。例えば、コンペで出会う監督たちとは『僕があなたの国に行ったらサポートして欲しい。代わりに、日本で撮影を行う場合は協力する』といったコミュニケーションがとれたらいいなと。映画祭は、参加したら終わりではなく、あくまで“過程”だと思っているんです』
福永監督「日本の宣伝における映画祭の扱われ方について、個人的に思っていることがあります。映画祭に出品したという事実だけを“スタンプ”のように利用し、日本での配給の勢いに使う。これが最大の目的のようになっているような印象を受けるんです。本来の映画祭は、監督同士で交流し、そこでの経験を持ち帰り、次へと繋げていく場所だと思うんです。祝いの場でもあり、映画文化を広めるために、さまざまなことを共有する場でもあります』
今泉監督「俺、英語が喋れないんですが、だからこそ英語を話せるスタッフの方が、要所要所で傍にいてくれるといいのかもと思いました。それは頼めばできることなのかもしれないけど、これまで積極的にお願いをすることはなかった。せっかく“交流”できる場なのに、結構損をしていますよね。もちろん自分が喋れるようになるのが一番良いんですけど……。海外の映画祭に行った時、『このタイミングで、あの人と喋れないのはもったいない……』なんて悔しく感じることが何度もありましたから」
●日本で一番大きな映画のイベント=今の日本映画界のイメージに深く関わる
続けて、松永監督は「映画祭は“過程”である」という発言を、さらに掘り下げていく。
松永監督「映画祭は、マーケットの場でもありますよね。日本のプロデューサーには『この映画を海外に売っていく』という意識が、まだ低いような気がしています。僕らは人生をかけて、映画を作っているわけです。映画祭は、発表の場としても機能し、作品に関わった人々の“その後の人生”にも大きく関わっていく。『そこまで課すのは、暑苦しい』と言われてしまうかもしれませんが、そうあるべきだと思うんです。ひとつひとつ変化をしていかなければ、日本映画や東京国際映画祭の在り方は変わっていかない。コンペに入ったことで、ようやくこういうことが言える立場になったのではないかと思っています。日本人監督として、この国の一番大きな映画祭とどう向き合っていくべきなのか。ここには、責任があるのではないかと考えています」
今泉監督「福永監督が仰った“スタンプ”の話は、日本の映画が国内を向き過ぎてしまっているという面もありますよね。作り手も、宣伝や配給側も“国内で完結”という意識であれば、それ以上は絶対に広がっていかない。もちろん作品を過信したり、過剰に評価するべきではなく、あくまで冷静に判断するべきではあります。ただ、これまでの東京国際映画祭でも、コンペや他部門に選出された作品が、さまざまな国の方の目に触れたことで、世界に羽ばたいていった事例がたくさんあります。どう広げていくべきなのか――これを作品に関わる人たちが考えているか、考えていないかで結果は異なるはず」
福永監督「映画祭は、さまざまなことを発信して、映画文化全体への理解を深めることができる場でもありますよね。日本で一番規模の大きい映画祭が、しっかりとした“映画祭のモデル”になることで、広がる効果ってたくさんあると思うんです。それに、海外からいらっしゃる方にとっては、今の日本の映画界の印象にも直結しますよね。『日本で一番大きな映画のイベントは、こういうものなのか』と。このイメージは、現在の日本映画業界の印象に深く関わってしまう。そういう意味でも内だけを見るのではなく、外に向かっていくということは大事なのかもしれません」
●宣伝&メディアの在り方とは?「それぞれの持ち場で意識を変えるべき」
監督陣の議論は、作品を巡る宣伝、メディアの在り方にも展開していった。
松永監督「日本の宣伝というものは、『こういう映画だから、こんな宣伝にしましょう』とベルトコンベア式に流れているような印象を受けています。そこも変わっていかないとダメだと思います。作り手の表現や認識は、時代に合わせて変わっていかないといけないと言われて、色々なことを課されながらも、そのなかで試行錯誤しながら作っている。そうして、作った後、劇場で上映されるまでの手法というものが、恐ろしいほど変わっていません。その点も、映画祭の在り方と深く関わっているように思えるんです。なるべく宣伝にも意見するようにはしていますが、僕ら監督にも限界というものはあります。宣伝に携わる方たちが、どのように東京国際映画祭を良い意味で利用するのか。皆がそれぞれの持ち場で意識を変えていかないと」
今泉監督「“大きい話”になってしまいますが、『映画というものを、今の日本の映画業界、マスコミがどうとらえているのか』という部分にまで戻ってしまうのかもしれませんよね。商業的・興行的な部分は、もちろん無視できないものです。しかし、本当に内向きな作品が圧倒的に多い。見やすさやテンポなどを求められることも多々あります。製作した映画を、関わった人々がどう思っているのか――この意識次第で、見せ方も変わってくる気がしています。例えば『三大映画祭の受賞作品は、ヒットするのか?』という点にも繋がってきますよね」
松永監督「日本の興行では“良い映画がヒットする”とは言えず、カンヌ、ベルリン、ベネチアで高評価を得た作品も、日本で観てもらえるかと言えば、決してそうではない。その一方で“三大映画祭の評価が全て”かといえば、それも違うはず。日本のマーケットの特殊性というものは、かなりあると思います。だからこそ、どう上手く宣伝していくのかが重要です。それと、今回のラインナップ会見、首を傾げてしまった光景があるんです。それは、メディア向けのQ&A。思ったよりも質問が出なかったですよね?」
今泉監督「海外の映画祭では、あまり見ない光景ですよね」
松永監督「そう、海外の映画祭であれば、制限時間ギリギリまで質問を投げかけられることが多いですよね。事前のインフォメーションが少なかったという、仕方のない部分もあるとは思いますが……例えば、僕が映画専門の記者をしているのであれば、過去作を引き合いに出しつつ、新作ではどのようなアプローチを行ったのかといった質問を投げかけると思います。ラインナップ作品、映画祭そのものについて、さまざまな角度で興味をもってもらえるよう、積極的に関わっていただきたいです」
福永監督「監督の立場から見た時に『それは間違っているのではないか』と感じてしまう部分を、映画祭という場では、可能な限り無くして欲しいという思いがあります。例えば、舞台挨拶におけるバラエティ番組のようなトーク。肝心の映画の話がまったくできないという場合が多々ある。映画に特化したサイトでも、映画自体に関係のない部分を強調してしまうことがありますよね。映画祭として様々な面において“良いモデル”を発信できれば、映画業界全体に良い影響を与えてくれるのではないかと思っています」
今泉監督「そもそもマスコミが映画に興味がないんですよね。いや、興味があってもそれを発信できにくい土壌が当たり前になってしまっていて、俳優の話などだけが取り上げられることが多い。これはつくり手の責任でもあるけど、日本における映画の置かれている位置、立場を本当に変えていきたいし、それを手伝ってほしいです、切に」
●これからの東京国際映画祭について――日本映画に対して「まだ諦めていない」
手掛ける映画のタイプは、それぞれ異なったもの。しかし、日本映画に対して共通の思いを抱えている――松永監督は、今回のてい談を通じて、そう確信したようだ。
松永監督「こうやって3人で話をさせて頂いて感じたことは、僕たちは日本映画に対して『まだ諦めていない』というもの。『松永、しょうがない。日本映画はこういうものだから』。そんな寂しい言葉を上の世代から聞くこともありました。長年、悔しい思いをし続け、闘えば疲弊していくというのもわからなくもありません。それは、生きていくための術なのかもしれません。でも、今ここにいる3人は、諦めていないんですよね。自分の映画だけでなく、日本の映画そのものについて『もう少しこうあるべきなのではないか?』と言い続けたい。“言葉を発する”というのは、結構しんどいことなんですけどね。
今泉監督「言葉というものは、自分自身に返ってきてしまいますからね」
松永監督「そうなんです。何かを発信しようものなら『では、お前はどうなんだ? 面白い映画を作れよ』と言われてしまう。でも“諦めていない人たち”がコンペに選ばれたというのは、映画祭が変わっていく兆候のひとつなんじゃないかと。今泉監督も福永監督も、まだまだ言いたいことはいっぱいあるはず。そういう人たちがいることは、ひとつの希望のような気がしています。
今泉監督「松永監督、福永監督のように、しっかりと海外を視野に入れた人がコンペに選ばれたという事実は、今回大きいことなんじゃないかなと思います。これまで思ってはいたけれど、なかなか言葉にすることが出来なかった――そんなことをいっぱい聞けたような気がしていて。そこに感動しています」
松永監督「東京国際映画祭は、海外の主要な映画祭と比べると『レベルが低い』と思う人もいるかもしれません。でも、コンペティション部門に関していえば、日本映画がグランプリを獲ったのは2回だけ(第1回『台風クラブ』相米慎二監督、第18回『雪に願うこと』根岸吉太郎監督)。かなり現実的な結果を突きつけられているんです。だからこそ、日本の映画が“本気で賞を獲りにいく”という気持ちで参加することが、東京国際映画祭を変える要素のひとつになる。この意識が、かなり必要なことだと思っています。その前提で他国と競い合い、メインの賞に絡んでいく。それが出来てくれば、映画祭の見られ方というものも変わっていくのかもしれない。審査委員は、海外の方が中心ですし、そこにはなんの忖度もない。日本だろうが、海外だろうが、平等に映画を観てくれますから。“良質”の中で競い合っている――そんな見られ方がされるようになればいいなと思っています」
第35回東京国際映画祭は、10月24日~11月2日、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区で開催。オープニング作品『ラーゲリより愛を込めて』(瀬々敬久監督)で幕を開け、クロージング作品には『生きる LIVING』(オリバー・ハーマナス監督)が控えている。