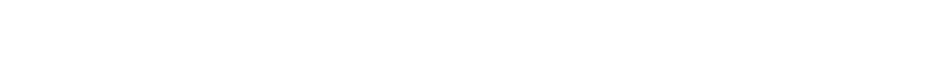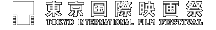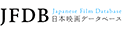10/29(土) ワールド・フォーカス ツァイ・ミンリャン監督デビュー30周年記念特集『水の上を歩く/西遊』上映後、ツァイ・ミンリャン監督、リー・カンションさん(俳優)をお迎えし、Q&Aが行われました。
⇒作品詳細
司会:石坂健治シニア・プログラマー(以下、石坂SP):それでは監督からご挨拶をお願いいたします。
ツァイ・ミンリャン監督(以下、監督):皆様お疲れ様です。この作品は美術館向きであるのですが、私はこのような作品を、こうして劇場で上映していただけるのをとても嬉しく思っております。最初から最後まで全部観ていただけるからです。この作品のシリーズは、既に9本撮っております。このシリーズは、パリのポンピドゥー・センターで特集上映されます。皆さんには先にこの新作を観ていただきました。ありがとうございます。
石坂SP:では、リー・カンションさんお願いいたします。
リー・カンションさん(以下、リーさん):一番お疲れなのは私だと思います(笑)。皆様は観ながら少し居眠りしたりもできます。この作品は、台湾の宜蘭県(イーラン/ギーラン)の壮囲郷(ジュワンウェイ)という砂丘のところに美術館があって、そこで公開されたものです。もし台湾に行く機会がありましたらぜひ宜蘭県にも行かれてください。
石坂SP:監督の30周年を振り返るということで、これはやはり最近の作品では欠かせないシリーズですので、こういうプログラムになりました。先ほど、最初は演劇版だったとお聞きしました。
監督:私の作品は、一本一本作ってきたというのではなく、一本一本育ってきたというような感じです。『ヴィザージュ』という、私がかつてパリのルーブル美術館からお招きいただいて撮った作品があるのですが、私は元々舞台の出身で、リー・カンションを主演にした舞台を一本制作しました。この舞台は時間は100分ほどなのですが、そのうちの30分は、今皆さんに観ていただいたような、ひたすらリー・カンションが歩き続けているというシーンなのです。音楽もセリフもなにもありません。その中でひたすら歩いています。この舞台を観て、リー・カンションの歩く姿に非常に感動して、この美しい歩く姿を舞台だとその場で終わって残すことができないので、何とか残すため、映画にして撮っておこうと思いこのシリーズになりました。私はこの各世界のいろんな片隅でリー・カンションが歩いている姿を残しておきたいと思いました。それはまるで、約1400年くらい前に、唐の玄奘が西安を出発してインドに経典を取りに行き、十数年経ってやっと帰ってきたというような歴史上の人物がおりました。ですので、リー・カンションの歩くという行動から世界を理解することができるというわけです。そういう風に撮りたいと思っていたときに、不思議なことにお金がやってきました。そのように一本ずつ撮り続けてきてもう10年以上になります。ですので、これを総合すると、私の映画人生のなかで一番長い作品です。これからまた彼が10年歩き続けて、それからもっと歩き続けていったら、まだまだ行った先というのは私たち二人のうちの一人がもういなくなってしまったときかもしれません。
石坂SP:リー・カンションさん、この役は慣れましたか?それとも未だに大変ですか?なにか歩くコツのようなものはあるのでしょうか?
リーさん:最初の頃は観客に、歩いているときに何を考えているのですかとよく聞かれました。そのとき私は、監督はなぜまだカットをかけないのだろうかと思っていたと答えました。毎回ひたすら歩くのが10分以上、あるいは20分以上というような長い距離なのです。その後、私は仕方がないので気力、どうしようもないときは心でお経を唱えながら歩きました。そして特にこの『水の上を歩く』をマレーシアで撮影したときは、非常に暑くて、だいたい気温が40~50℃くらいありました。そこを4日間くらいで撮影したのですけれども、足の裏に50か所ほど水ぶくれが出来てしまいました。このシリーズの中で、東京で撮影した作品があるのですが、そのときは逆に寒くて、1~2℃くらいしかありませんでした。そのまま裸足でコンクリートや鉄の上を歩くのですけれども、ほとんど氷が張っているような状況で歩き続けて、すごく寒かったです。香港で撮影したときは蚊に狙われて、ずっと蚊に付きまとわれていました。蚊を意識して、たたいたり追い払ったりすることができないので痛めつけられながら歩き続けました。マルセイユで撮影したときは、ある女性の方が私の歩く姿を見てお金を恵んでくれました。フランスのお金で2ユーロくらいくれました。ですが、これはまずいと思い、もう一度撮り直しました。いつもこの作品を撮るときは、とても辛くて大変なのですが、色々なところで撮影ができて、面白いと思っています。
Q:初期の作品と最近の作品では印象が異なるように感じました。初期から現在にかけて、それから、商業映画と美術館で上映される短編について、扱うモチーフや変化があったかについてお聞きしたいです。
監督:(質問者に)年齢をお聞きしてもよろしいですか?
Q:22歳です。
監督:そうですか、嬉しいですね。こういう新しい若い観客に観ていただけるのは嬉しいです。ですので、賞味期限が長いなと思います。最近アメリカに上映ツアーに行きまして、4つの都市を回ってきました。やはり同じような情景に出くわしました。そのツアーで非常に嬉しかったのは、多くの観客が私の過去の作品では無く最近の作品を話題にしてくださったことです。私の新しい作品に非常に興味を持っていらっしゃいました。私はずっと映画を新しい物、新しいスタイルという物を模索していきたいと思っているので、あまり商業的な物に寄るのに興味はありません。そして私のそういう特性があるものですから、私の初期それから中期に至って台湾の芸術界でもやっと関心を持ってくれるようになりました。最初は本当にあまり注目されませんでしたが、世界で色々賞をもらいますけれども注目されないということです。そしてこの『楽日』になってやっと興味を示してくれました。ですので、私は美術館と提携して自分の芸術の可能性を広げていきたいと思うようになりました。そのことによって私は大きな自由を獲得しました。そうこうするうちに私は次第に劇映画に興味を失うようになりました。完全に興味が無いというわけでもありませんけれども、薄くなってきたわけです。そして美術館の方向へと向かっていきました。ですけれども私は映画館という物にとても捨てきれない思いがあります。私はこの映画館という暗い一つの箱の中に多くの観客が集まっているということにとても興味を惹かれます。そして映画館がそういう場所であるということが私をいつも惹きつけているものですから、私は作品を映画館で観てもらうということには非常に興味を惹かれています。いろんな可能性があると思います。
Q:監督にお聞きしたいことが100くらいありますが、一つに絞りますと、この行者が歩いている時の頭の動きについてお教えください。
監督:このシリーズで9本撮っていますから、もし9本とも全部ご覧になったらリー・カンションの頭の動きが全部違っているということがわかると思います。毎回、リー・カンションの撮影時の生理的な状況とかそういうことです。ある作品を撮る時、リー・カンションは病気になっていて首を痛めていました。その首を庇うように歩いていると頭もそういう風になっていると思います。
100くらい質問があるとおっしゃっていて驚きました。自分で作品を撮ってほとんど疑問はないのですけれど。やはり映画、芸術というのは答えというものが必ず必要なものではない。観る人もそうですし、撮る側にとってもその答えが無いかもしれない。この「ウォーカー」シリーズの行者が歩く姿を見る時、私と同じような気持ちで観客のみなさんが観てくださると嬉しいですね。それは修行をしていくということです。この映画の中でリー・カンションの歩く速度は非常にゆっくりとしています。どうでしょう、我々も心をゆっくり鎮めてはどうでしょうか。そしてゆっくりとした静かな心持ちで、世界が本来どういう状態であったのかということを見るのはどうでしょうか。おそらくいろんな国、いろんな場所が違っているという風に思います。それから自分のことを考える。それが、私がこの作品に込めた思いです。ありがとうございます。