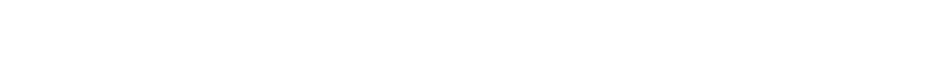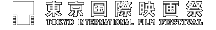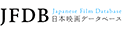東京国際映画祭公式インタビュー:
『テルアビブ・ベイルート』
ミハル・ボガニム(監督/脚本)

©2022 TIFF
キリスト教勢力とイスラム教勢力の政治的・宗教的な対立が続いて、世界の縮図とも呼ばれるレバノン。この国は1975年に内戦が勃発し、その3年後には国境を接するイスラエルの軍隊が南部地域に侵攻。以降、イスラム武装組織ヒズボラとイスラエル軍が戦闘を行い、イスラエル軍が撤退した今日も政情不安にさらされている。
本作はこの歴史背景を通じて生じたさまざまな苦悩を、国境をまたぐそれぞれの側の女性から見つめ直し、戦争の悲惨さを世に問う一作。学校の帰り道で戦争が起こっている異様さや、現代イスラエルのアンニュイな不倫事情(その男性役を演じているのは世界的なジャズ演奏家にして、本作の音楽を担当したアビシャイ・コーエンである)など、細部に意外な展開があり、レバノン人のタニヤとフランス系のイスラエル人ミリアムのめぐりあいも、映画的にうまく醸成されている。
監督のミハル・ボガニムは今年38歳。フランス国籍を持つイスラエル人で、『故郷よ』(11)が2013年に日本公開されており、本作は、およそ10年振りの監督第2作となる。
――前作の『故郷よ』(11)でチェルノブイリ事故の被害に遭ったウクライナ人を描き、本作では南レバノンの戦争に巻き込まれるイスラエル人を描いています。監督は母親がウクライナ系の方で父親がイスラエル人です。いずれも自伝的要素を作品に反映させているのでしょうか?
ミハル・ボガニム監督(以下、ボガニム監督):そうです。私の父は戦争を経験しており、私もイスラエル生まれということで、戦争は常に身近にある問題でした。本作ではほんとうに、自分が経験したことを描きたかったのです。
――レバノンにはキリスト教徒とイスラム教徒がおり宗派間の対立が激しいですが、幼い頃からタニヤとカマルは宗派を越えて好意を持ち、互いに愛を育みます。こうした恋愛はしばし見られることなのでしょうか?
ボガニム監督:あまり一般的ではないけれど見られます。
――幼いタニヤを演じているのは?
ボガニム監督:11歳になる私の娘です。残念ながら、彼女は女優になりたいんです。(笑)

――南レバノンから命からがら逃げてきた人々を、イスラエルは国境を封鎖してなかなか受け入れません。なぜすぐに受け入れてやらないのでしょう?
ボガニム監督:あれはイスラエルの背信行為です。あの地を占領していたイスラエル軍が撤退し、親イスラエル感情をもつキリスト教徒のレバノン人は見捨てられました。それで、タニヤと彼女の父親のフアドはイスラエルに逃げますが、すぐに受け入れてもらえずショックを受けるのです。
――2006年にこの国境付近で、ふたりのイスラエル人兵士がヒズボラに誘拐され、2年後に行われた捕虜交換で棺に収まって引き渡される、とても痛ましい出来事がありました。ザルイート村で起きたこの事件をもとにしたのですか?
ボガニム監督:そうです。
――ふたりの女性の視点から、戦時下における日常と激変する生活を描いています。どんな思いを託したのでしょう?
ボガニム監督:異なる国の異なる人種、異なる世代。そして戦争の犠牲者であるということです。戦争になれば、女性が犠牲を払うことを象徴させました。
――イスラエルから助成金は出なかったのですか?
ボガニム監督:申請したけど却下されたんです。
――「反兵役」をテーマのひとつに据えているからですか?
ボガニム監督:恐らくそうでしょうね。
――撮影監督のアクセル・シュネバットさんはドイツ人の方ですね。
ボガニム監督:ハイム・タベクマン監督の作品でイスラエルでも撮影したことのある方で、もう長いこと知り合いなんです。彼の撮影は素晴らしいので依頼しました。
――この映画は音楽映画という要素も強くあるように思います。映画で音楽が果たす役割について、監督はどのようにお考えですか?
ボガニム監督:感情に何か訴えるというよりは、ムードを醸し出したいと思って音楽は使っています。本作の音楽については、緊張感を際立たせることと、センチメンタルになりすぎないことを意識しました。
――最後にこの作品で最も伝えたかったことは?
ボガニム監督:戦争というものは、何世代にもわたって影響を蒙るものであり、尾を引いていくものである。そう伝えたかったのです。
取材/構成:赤塚成人(四月社)・松下由美
第35回東京国際映画祭 コンペティション部門
『テルアビブ・ベイルート』

© 2021 MOBY DICK FILMS – LES FILMS DE LA CROISADE – TWENTY TWENTY VISION Filmproduktion – TEL AVIV BEIRUT AVC LTD – LA VOIE LACTÉE
監督:ミハル・ボガニム
キャスト:ザルファ・シウラート、サラ・アドラー、シュロミ・エルカベッツ
東京国際映画祭公式インタビュー:
『テルアビブ・ベイルート』
ミハル・ボガニム(監督/脚本)

©2022 TIFF
キリスト教勢力とイスラム教勢力の政治的・宗教的な対立が続いて、世界の縮図とも呼ばれるレバノン。この国は1975年に内戦が勃発し、その3年後には国境を接するイスラエルの軍隊が南部地域に侵攻。以降、イスラム武装組織ヒズボラとイスラエル軍が戦闘を行い、イスラエル軍が撤退した今日も政情不安にさらされている。
本作はこの歴史背景を通じて生じたさまざまな苦悩を、国境をまたぐそれぞれの側の女性から見つめ直し、戦争の悲惨さを世に問う一作。学校の帰り道で戦争が起こっている異様さや、現代イスラエルのアンニュイな不倫事情(その男性役を演じているのは世界的なジャズ演奏家にして、本作の音楽を担当したアビシャイ・コーエンである)など、細部に意外な展開があり、レバノン人のタニヤとフランス系のイスラエル人ミリアムのめぐりあいも、映画的にうまく醸成されている。
監督のミハル・ボガニムは今年38歳。フランス国籍を持つイスラエル人で、『故郷よ』(11)が2013年に日本公開されており、本作は、およそ10年振りの監督第2作となる。
――前作の『故郷よ』(11)でチェルノブイリ事故の被害に遭ったウクライナ人を描き、本作では南レバノンの戦争に巻き込まれるイスラエル人を描いています。監督は母親がウクライナ系の方で父親がイスラエル人です。いずれも自伝的要素を作品に反映させているのでしょうか?
ミハル・ボガニム監督(以下、ボガニム監督):そうです。私の父は戦争を経験しており、私もイスラエル生まれということで、戦争は常に身近にある問題でした。本作ではほんとうに、自分が経験したことを描きたかったのです。
――レバノンにはキリスト教徒とイスラム教徒がおり宗派間の対立が激しいですが、幼い頃からタニヤとカマルは宗派を越えて好意を持ち、互いに愛を育みます。こうした恋愛はしばし見られることなのでしょうか?
ボガニム監督:あまり一般的ではないけれど見られます。
――幼いタニヤを演じているのは?
ボガニム監督:11歳になる私の娘です。残念ながら、彼女は女優になりたいんです。(笑)

――南レバノンから命からがら逃げてきた人々を、イスラエルは国境を封鎖してなかなか受け入れません。なぜすぐに受け入れてやらないのでしょう?
ボガニム監督:あれはイスラエルの背信行為です。あの地を占領していたイスラエル軍が撤退し、親イスラエル感情をもつキリスト教徒のレバノン人は見捨てられました。それで、タニヤと彼女の父親のフアドはイスラエルに逃げますが、すぐに受け入れてもらえずショックを受けるのです。
――2006年にこの国境付近で、ふたりのイスラエル人兵士がヒズボラに誘拐され、2年後に行われた捕虜交換で棺に収まって引き渡される、とても痛ましい出来事がありました。ザルイート村で起きたこの事件をもとにしたのですか?
ボガニム監督:そうです。
――ふたりの女性の視点から、戦時下における日常と激変する生活を描いています。どんな思いを託したのでしょう?
ボガニム監督:異なる国の異なる人種、異なる世代。そして戦争の犠牲者であるということです。戦争になれば、女性が犠牲を払うことを象徴させました。
――イスラエルから助成金は出なかったのですか?
ボガニム監督:申請したけど却下されたんです。
――「反兵役」をテーマのひとつに据えているからですか?
ボガニム監督:恐らくそうでしょうね。
――撮影監督のアクセル・シュネバットさんはドイツ人の方ですね。
ボガニム監督:ハイム・タベクマン監督の作品でイスラエルでも撮影したことのある方で、もう長いこと知り合いなんです。彼の撮影は素晴らしいので依頼しました。
――この映画は音楽映画という要素も強くあるように思います。映画で音楽が果たす役割について、監督はどのようにお考えですか?
ボガニム監督:感情に何か訴えるというよりは、ムードを醸し出したいと思って音楽は使っています。本作の音楽については、緊張感を際立たせることと、センチメンタルになりすぎないことを意識しました。
――最後にこの作品で最も伝えたかったことは?
ボガニム監督:戦争というものは、何世代にもわたって影響を蒙るものであり、尾を引いていくものである。そう伝えたかったのです。
取材/構成:赤塚成人(四月社)・松下由美
第35回東京国際映画祭 コンペティション部門
『テルアビブ・ベイルート』

© 2021 MOBY DICK FILMS – LES FILMS DE LA CROISADE – TWENTY TWENTY VISION Filmproduktion – TEL AVIV BEIRUT AVC LTD – LA VOIE LACTÉE
監督:ミハル・ボガニム
キャスト:ザルファ・シウラート、サラ・アドラー、シュロミ・エルカベッツ