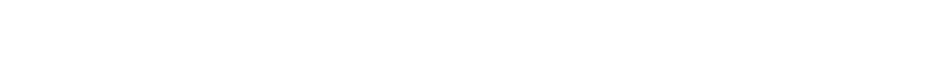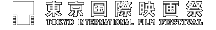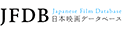来日したイニャリトゥ監督、自叙伝的な最新作は「作らざるをえなかった映画」 二重の存在である移民を描く

「黒澤明監督愛」もたっぷり語ったアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督
第35回東京国際映画祭のガラ・セレクション部門に出品された『バルド、偽りの記録と一握りの真実』の会見が10月29日、東京・有楽町のBASE Qホールで開催され、来日したアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督が登壇した。敬愛する黒澤明監督への愛、移民を描き、「作らざるをえなかった映画」と語った最新作について、トークを繰り広げた。
本映画祭でイニャリトゥ監督は、14年ぶりに復活した「黒澤明賞」を受賞。「『アモーレス・ペロス』がこの映画祭で上映されたときの初来日から22年を経て、この名監督の名を冠した賞を受けとる。いままで存在した監督のなかでも最高峰のおひとりで、私が崇拝するアイドルといえる方の賞を受けとることは、大いなる喜びです」と、胸中を明かす。イニャリトゥ監督の黒澤監督愛は相当なもので、影響を受けた作品について、たっぷりと語った。
「父が、私が若い頃に『羅生門』を勧めてくれました。その非常に独自の視点は、私に映画を見るうえでのある種の目覚めをもたらしてくれました。また『羅生門』は、『アモーレス・ペロス』に大きな影響を与えています。つまり、ひとつの出来事をさまざまな視点で見る、経験する。その異なる視点を、映画に投影する。そういったことを、黒澤監督は『羅生門』で見せてくれて、私も“第3の目”で見ることを学びました。『生きる』も何度も拝見し、大きな影響を受けました。私はバルセロナで、ハビエル・バルデム主演で『BIUTIFUL ビューティフル』を撮りましたが、精神性において、共通するものがあると感じます」
「さらに、『七人の侍』『乱』からも、大きなインパクトを受けました。スペクタクルなアクションを、ほかの監督が撮ったことのない至近距離で、迫ってくるように撮っていることに触発されました。大きな叙事詩だが、キャラクターの感情は自分に近いものを感じるという描き方のユニークな点、パワフルな面、人間性といったものを学び、私は同じことを『レヴェナント 蘇えりし者』で達成しようとしました」
黒澤監督トークが止まらない様子のイニャリトゥ監督。尊敬しているところを問われ、「黒澤監督作品から伝わるものは、魂を深く理解すること、何が人間を深く突き動かすのかということ、そして人間の矛盾。黒澤監督作品は、さまざまな矛盾を抱え、立体的に造形され、安易な結末に走らない。そして、映画文法という点では、身体的な面と精神的な面が、同じ空間に同居している。メランコリーという人間の精神が表現されています」と解説。さらに、黒澤監督が自身を「発展途上の学生だ、いろんな実験をしている」と語っていた映画人としての在り方に触れ、「私は若い映画作家として、こんな映画の巨人が、なお未知の部分を探索していく精神であること、あとはリスクを恐れず、あえて失敗にも飛び込んでいくところなど、作品と人間性に敬意を表しています」と、最敬礼していた。
そんなイニャリトゥ監督の最新作『バルド、偽りの記録と一握りの真実』は、ある男の心の壮大な旅路を描く、自叙伝的なノスタルジックコメディ。製作のきっかけについて、「私の以前の作品で探究したテーマは、「移民・移住」で、大きく目を見開いて製作しました。ですが今回は、目をつぶって作った、つまり非常に内省的な旅です。自分の感情、夢、考え、恐れ、後悔、そして過去、未来、現在、全てが混在して編み込まれて、ひとつのものを織り成すという形です。私にとって、作らざるをえなかった作品です。私は21年間アメリカで、移住者として生きてきました。(中略)私は祖国を出て、ある意味、そこに何かを置いてきた。二重の存在、ふたりの自分がいるようで、どちらにも属していない、もう戻ることはできないんです」と、思い入れの強さをにじませる。
タイトルの「バルド」とは、チベット仏教用語で、「自分のアイデンティティの置き場がない」という意味。「いかに恵まれ、成功したとしても、移住者が感じる何らかのノスタルジー、メランコリーを共有頂けるのではないかと思います。そういう部分にアプローチするには、ユーモアの手法をとる必要があり、魂の傷を癒す撮り方をしています」と振り返った。
本作は、イニャリトゥ監督の母国メキシコで撮影され、主人公は映画製作者であるなど、自伝的要素が濃い。「この映画は特殊で、個人的な視点と実体験を多く用いている。そう話すと皆さんは、バイオグラフィと感じるかもしれませんが、そもそも私は、バイオグラフィというものを信じていません。バイオグラフィといっても嘘や偽善的な内容が含まれていたりして、結局「真実とは何か」という問いになるわけですね」。最後にイニャリトゥ監督は、本作を経て感じたフィクションの作用や、次回作のビジョンについて述べた。
「この作品は非常に内省的な旅路であり、記憶というものは記憶であり、真実が抜け落ちている場合もある。本作ではあえて、現実を欺く。フィクションであるということは、ある意味、真実をより昇華して、高いところにもっていけるわけです。フィクションには、リアルだと銘打って、隠れているものをあぶりだす作用があると考えています。本作は、現実と空想の間を漂う作品といえるかもしれません。こういう作り方をすると、ポジティブな影響が出てきて、自分の無意識下にあるもの、自分では覚えていたくない、居心地が悪い記憶なども出てくる。こういうものは、発想の源として、素晴らしい題材だと感じました。自分のなかにあるこの素材を見せられたので、負担になる部分もありますが、それをフィクションに生かしたいと思いました。次回作は、そこから発展させていけたらと思います」
『バルド、偽りの記録と一握りの真実』は、11月18日から一部劇場で公開され、12月16日にNetflixで配信。第35回東京国際映画祭は11月2日まで、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区で開催される。
新着ニュース